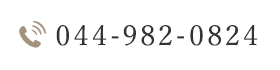慢性的な下痢・便秘
 本来、便はバナナ状で一定の硬さと量を持ち、一定のタイミングで排泄されるものです。
本来、便はバナナ状で一定の硬さと量を持ち、一定のタイミングで排泄されるものです。
排泄間隔や量、硬さ、性状が変化し、排便がスムーズにできなくなる状態を便通異常と言います。
便通異常は2つあります。
1つ目は、普段の便より柔らかく、回数も頻繁になる下痢で、2つ目は排泄間隔が長くなったり、排便しても残便感があったりする便秘です。
誰でも食べ過ぎやお腹を冷やすことで下痢になったり、風邪で便通が数日間なかったりすることがあります。
しかし、原因がはっきりせず下痢や便秘が続いたり、便秘と下痢を繰り返したりしている場合、消化器疾患や過剰なストレスが影響している可能性が考えられます。
いつもと異なる便通異常が続く場合は、市販薬だけでごまかさず、できるだけ早く受診することをおすすめします。
今までの知見と臨床経験を活かし、患者様それぞれに異なる便通異常の原因を正確に導き出し、適切な治療を提供します。
お気軽にご相談ください。
下痢
下痢について
 便中の水分が通常より増えて液状や泥状の便が出る状態です。
便中の水分が通常より増えて液状や泥状の便が出る状態です。
排便回数も増加することが多いです。
理想とされるバナナ状の便は、水分量が便量の70~80%程度ですが、これより水分量が増えて90%程度までを軟便、さらに90%を超えると水様便(下痢便)となります。
このような下痢があった場合はご相談ください
- 急に普段より激しい下痢が起こった
- 下痢だけでなく吐き気や嘔吐もある
- 下痢だけでなく発熱もある
- 下痢便の中に血が含まれている
- 下痢によって脱水症状を起こしている
- 排便後でも腹痛が続く
- 下痢が止まらず、段々悪化している
上記のような症状がある場合は、まずは当院へお越しください。
感染性の下痢の場合、市販の下痢止め薬を使用すると逆に回復が遅れてしまう恐れもあります。
安易な服用は避け、まずご相談ください。
下痢が起こる原因
下痢は2週間以内に改善されるものを「急性下痢」、4週間以上も長引くものを「慢性下痢」、その間の期間(2~4週間)で治るものは「遅延性下痢」と呼ばれています。それぞれ原因も異なります。
急性下痢
ほとんどの場合、ウイルスによる感染性胃腸炎が原因です。次いで、細菌感染やお酒の飲み過ぎなどが多いとされています。
慢性下痢
小腸や大腸に何らかの疾患があって起こることが多いです。
主な原因疾患としては、クローン病や潰瘍性大腸炎といった炎症性腸疾患、過敏性腸症候群などの機能性胃腸症があります。
また、大量飲酒や水分の過剰摂取、内服薬の副作用、ストレスなどの精神的な原因も考えられます
2週間を過ぎても下痢が治まらず、1ヶ月以上続く場合は、市販の下痢止めをなるべく使用せずに当院へご相談ください。
下痢を起こす病気について
ウイルス性胃腸炎
ウイルス性胃腸炎は、ウイルス感染によって急激に発生する胃腸炎のことを指します。
症状は、下痢をはじめ、吐き気、嘔吐、腹痛といった胃腸症状が主体ですが、発熱などの全身症状が起こることもあります。
原因となるウイルスは、ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなどが挙げられます。
クローン病
クローン病は、口から食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、そして肛門にまでおよぶ、原因不明の炎症がランダムに発生する炎症性腸疾患の1つです。
ほとんどは小腸と大腸の接合部付近で発症し、広範囲に炎症によるびらんや潰瘍が現れる活動期(再燃期)と、症状が落ち着く寛解期が交互に繰り返されます。
自覚症状としては、下痢、腹痛、食欲不振などが挙げられます。
自己免疫が関与していると考えられていますが、現在のところ完治に導く治療法はまだ確立されていません。
そのため、国の指定難病として定められています。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に原因不明の炎症が発生し、下痢、腹痛、粘血便などの自覚症状が目立つ活動期(再燃期)と、症状が落ち着く寛解期を繰り返す指定難病です。
発症要因として自己免疫が関与しているとされており、クローン病と同じように炎症性腸疾患に分類されています。
ただし、炎症が大腸に限られている点と、直腸から発症して肛門から奥へ奥へと連続的に進行する点は、クローン病と大きく異なります。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群は、腹痛に加えて便秘や下痢、便秘と下痢の繰り返し、お腹の張りや慢性的なガスといった便通異常が長期間続く疾患です。特徴的なのは、排便後に症状が軽減されることです。
しかし、大腸検査を受けても炎症や器質的病変、内分泌機能の異常が見当たらないことが多いです。
原因としては、腸の蠕動運動や知覚機能がストレスなどの要因で障害されて発症するとされています。
適切な治療をすれば、少しずつ改善していくことが多いです。
大腸がん
大腸がんは発症しても早期ですと自覚症状がほとんど起こりません。
しかし、進行してがんが大きくなると、便の通過を妨げるため、便秘が続いた後に下痢となる、または柔らかい便しか出なくなるといった便通障害が起こりやすくなります。
下痢の検査
下痢の原因は、病原体の感染、腸そのものの疾患、薬剤、食物の影響など多岐にわたります。
その原因を特定するために、まずは問診を行い、直近の食事や生活状況、下痢以外の症状の有無、既往症、アレルギー、服薬中の薬などを丁寧にお伺いします。
感染や炎症の可能性が疑われる場合は血液検査を行い、器質的な病気が疑われる場合は内視鏡検査が可能な消化器内科にご紹介することもあります。
下痢の治療方法
 原因を考慮して選択します。
原因を考慮して選択します。
急性下痢でウイルスが原因の場合、水分補給をしながら安静に過ごすのに加えて、整腸剤などによる対症療法を実施します。
細菌感染が疑われる場合は、整腸剤だけでなく、必要に応じて抗菌薬を処方することもあります。
薬剤性の場合は、服用中の薬を一時休薬したり、代わりとなる薬を処方したりします。
慢性下痢の場合、そのほとんどは何らかの腸の疾患によるものです。
原因となる疾患を特定し、それに合わせた治療を開始します。
検査の結果、器質的・内分泌的な異常がないと確認された場合は、過敏性腸症候群の下痢型や混合型が疑われます。
その場合は、生活習慣の見直しや腸の機能を回復する薬物療法を選択します。
便秘
便秘について
 便秘とは、患者様にとって必要な便の量を一定の間隔で、かつスムーズに排便できなくなった状態です。
便秘とは、患者様にとって必要な便の量を一定の間隔で、かつスムーズに排便できなくなった状態です。
運動不足や食事などの生活習慣によって便秘になることもありますが、病気の症状として便秘が現れるケースもあります。
便秘が起こる原因
便秘は、大きく分けて機能性便秘と器質性便秘の2種類に分類されます。
機能性便秘は、大腸などの炎症・閉塞といった器質的病変が確認できず、大腸の蠕動運動や便意を感じる知覚機能に異常が生じて起こります。
ストレス、食事の偏り、食事時間の乱れ、便意を我慢する習慣なども発症要因とされています。
器質性便秘は、大腸にがんやポリープ、炎症、癒着による閉塞などの明確な病変が原因で起こるものです。
どちらの場合でも、便秘があると肛門や直腸に大きな負担がかかり、便が長時間腸内に滞留することで腐敗しやすく、有毒成分が発生しやすくなります。
これにより身体への悪影響が現れるため、早めに受診することをおすすめします。
一番気を付けなければならないのは大腸がんの便秘
機能性便秘は、食事の量が少ない、食事時間が不規則、食事の偏り、運動不足による筋力低下、ストレスによる自律神経の乱れなどが原因で起こることが多いです。
一方、器質性便秘は、大腸の粘膜に何らかの疾患があり、それが原因で起こります。
特に大腸がんやその前がん病変である大腸ポリープは、成長すると便の通り道を狭くし、便秘の原因となることがあります。
当院は危険な便秘のサインを見落とさないよう、丁寧に診察をして、必要に応じて専門医療機関に検査紹介を行います。
便秘でお悩みの方はぜひ、お気軽にご相談ください。
便秘の診断基準
2023年に出版された日本消化器病学会の『便通異常症症診療ガイドライン2023』では、慢性便秘症の診断基準として以下の項目を定めています。
- 便秘症の診断基準:以下の6項目のうち、2項目以上に該当している。
- 慢性であることの診断基準:「6ヶ月以上前から症状が見られ、かつ直近3ヶ月間は上記の基準を満たしている」ただし、日常診療においては患者を診察する医師の判断に委ねる。
この条件を満たすことで、慢性便秘症の診断がつきます。
なお、表中のBSFSとは、便の状態の分類基準であるブリストル便形状スケールのことを指します。
| C1 | 排便の4分の1超異常で、兎のフンのような便または硬便(BSFSでタイプ1か2)が出た |
|---|---|
| C2 | 自発的な排便回数が週に3回より少ない |
| P1 | 排便の4分の1以上で、強くいきむ必要がある |
| P2 | 排便の4分の1以上で、残便感があった |
| P3 | 排便の4分の1以上で、直腸肛門の閉塞感や排便困難感があった |
| P4 | 排便の4分の1以上で、用手的な排便介助が必要になった(摘便・会陰部圧迫など) |
(参考:日本消化器病学会『慢性便秘症診療ガイドライン2023』)
便秘を引き起こす病気
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群(IBS)は、大腸の運動機能や知覚機能が何らかの理由で障害されることで発生する疾患です。
腹痛を伴った便秘、下痢、便秘と下痢の繰り返し、腹部の張りといった便通異常が特徴です。
発症要因としてはストレスが挙げられ、比較的下痢型は男性に多く、便秘型は女性に多く見られます。
腸閉塞症(イレウス)
腸閉塞症(イレウス)は、手術痕やがんなどの部位で癒着したり、捻れたり、運動機能が麻痺したりすることで大腸が詰まり、便やガスが進まなくなる状態です。便が詰まって出なくなります。
放置すると最悪の場合、腸管が壊死してしまうこともあるため、早急に緊急治療を受ける必要があります。
その場合は当院では提携先の高次医療機関に速やかにご紹介いたします。
大腸がん
大腸がんが大きくなると腸管が狭窄し、便の通りが悪くなるため、便秘が起こります。
大腸がんは特にS状結腸や直腸にできやすく、便が硬くなり、便秘が起こりやすくなります。
また、便が擦れて血便が出ることもあります。
急に便が細くなった場合は大腸がんが疑われます。
便秘の検査
便秘の原因は1人ひとり異なります。まず、何が原因で便秘を起こしているのかを見つけ出すため、問診で詳しい内容をお聞きします。
その後に、必要に応じて血液検査や内視鏡検査ができる医療機関に紹介をしたりします。
便秘の治療
 治療法は便秘の原因によって変わります。
治療法は便秘の原因によって変わります。
器質的・内分泌的疾患が原因の場合は、原因疾患の治療を選択します。
機能性便秘の場合、食事内容や食事時間、運動療法などの習慣を見直します。
また、必要な場合には、複数種ある下剤から患者様に適した薬剤を選んで処方します。