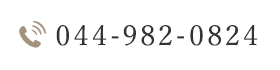気管支喘息とは
 気管支喘息は、気管支がアレルギーによって炎症を起こし、収縮して狭くなることで、咳、呼吸困難、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューと鳴る)などの症状が現れる病気です。
気管支喘息は、気管支がアレルギーによって炎症を起こし、収縮して狭くなることで、咳、呼吸困難、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューと鳴る)などの症状が現れる病気です。
アレルゲン(花粉やダニなど)、風邪、寒暖差、季節の変わり目、黄砂、精神的ストレス、アルコール摂取などによって症状が悪化しやすく、悪化と改善を繰り返すのが特徴です。
症状はある時もあれば、全くない時もあります。
また、夜間から早朝にかけて症状が悪化することが多いのも特徴です。
原因となるアレルゲンには、ダニ、ハウスダスト、ペット(イヌやネコ)、花粉(スギやイネ科)、カビなどがあります。
問診
喘息の診断において、問診は非常に重要です。喘息の症状には波があるため、普段は症状が出ていても診察時には収まっていることがあります。
そのため、症状がひどい時の状態を詳しくお伺いする必要があります。
診断のための問診では、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)、咳、喀痰、息苦しさ、胸痛の有無をはじめ、症状の変動について(特に朝や夜に症状がひどくなる)や季節による影響がないかもチェックします。
また、アトピー素因(アレルギー体質)や家族歴、喫煙歴、ペットの飼育歴(イヌ・ネコ・ウサギなど)も幅広くお聞きします。
さらに、アスピリン(解熱鎮痛剤)によって喘息が誘発されるケースもあるため、風邪薬の服用歴も確認します。
喘息の方に行う検査
気管支喘息の診断は、日ごろの症状の内容をはじめ、胸部Xp、呼気一酸化窒素(NO)濃度測定、特異的IgE抗体(アレルゲン検査)などの血液検査を参考に行います。
胸部Xp(胸部X線検査)
咳が長く続く場合には、肺炎や結核、肺がんなどの重篤な病気が隠れていないか検査を行います。
呼気一酸化窒素濃度測定(NO検査)
喘息の患者様は、気道の炎症により一酸化窒素(NO)を生成する酵素が増え、呼気中のNO濃度が高まる傾向があります。
日本人の成人健康者の正常値は約15ppbで、上限値は約37ppbです。
喘息を診断する場合、22ppb以上で喘息の疑いがあり、37ppb以上であれば喘息の可能性が極めて高いと判断されます。
ただし、鼻炎があると呼気NOが上昇し、喫煙は呼気NOを低下させるため、結果の解釈は慎重に行わなくてはなりません。
検査方法は非常に簡単です。
息を吐いた状態でマウスピースを咥え、大きく息を吸い込んだ後、一定の速度で息を吐き出します。
約1分程度で分析が完了し、結果が表示されます。
特異的IgE抗体
当院で対応可能なアレルギー検査
| 検査方法 | VIEW-39 | 単項目検査 |
|---|---|---|
| 検査結果 | 数日~1週間 | 数日~1週間 |
| 測定項目数 | 39 | 希望によって異なる |
| 採血量 | 5~10ml | 5~10ml(項目数によって異なる) |
| 測定項目数 | 39項目 吸入系・食物系・その他 |
3-6項目ほど |
| 料金(3割負担) | 約5000円 | 1項目:約330円 |
特異的IgE抗体検査は、アレルギーの原因物質を調べるための血液検査です。当院で行う検査方法は主に上記の2種類で、VIEW-39、単項目検査です。
患者様の希望や可能性のあるアレルゲン(原因物質)の種類に応じて検査を選択します。
治療
喘息治療の基本:吸入ステロイド
 気管支喘息の治療は主に吸入薬が中心となります。
気管支喘息の治療は主に吸入薬が中心となります。
気道の炎症を抑える吸入ステロイドと、気管支を広げる吸入気管支拡張薬が基本です。特に重要なのが、吸入ステロイドです。
吸入ステロイドは気管支の炎症を抑えることで喘息の症状を改善し、発作を予防します。
ステロイドと聞くと、何か副作用が恐いイメージを持つ方もおられるかもしれませんが、吸入薬は気道の表面に粉状粒子がついて局所の炎症を抑えることが主な働きであり、全身性に影響する内服薬とは違うので、正しく使用していれば恐れる必要は全くありません。
吸入ステロイドでの病状コントロールが困難な場合や、症状が長引く場合、治療導入初期などには、吸入ステロイド薬だけでなく、気管支拡張薬(β刺激薬・抗コリン薬)や抗ロイコトリエン拮抗薬なども併用します。
また、喘息の症状に応じて、吸入薬の量や吸入する回数を変更することもあります。
これらを行っても病状のコントロールが困難な場合には、生物学的製剤や内服ステロイドを検討します。
喘息治療では、毎日の吸入が不可欠です。継続して吸入を行うコツとして、1日の生活リズムに「吸入の時間」=「治療」とすることが大切です。
毎日同じ場所、同じ時間、同じ状況で吸入を行う習慣をつけます。例えば、洗面・歯磨きの前や朝食の前に吸入を行うなどです。
当院では、院内での吸入指導にも対応します。
適切な吸入方法と継続の重要性をしっかり説明し、患者様が効果的に治療を続けられるようサポートしています。
吸入薬の種類
吸入薬には大きく分けて2種類あり、粉末タイプの薬が入っているドライパウダー(DPI)と、ガスタイプの薬が入っている加圧定量噴霧式製剤(pMDI)があります。
ドライパウダー(DPI)は、ご自身の力で吸入するため、吸う力が弱い高齢者や子供には向いていません。
加圧定量噴霧式製剤(pMDI)では、薬の噴射のタイミングに合わせて吸入しなければなりません。
また、一部の薬剤にはエタノールが微量ですが含まれているため、アルコールに対して過敏に反応する方は要注意です。
ドライパウダー製剤によって声枯れや喉の違和感などの副作用が出た場合は、pMDIへの変更を検討します。
吸入する方法
吸入薬は、正しい方法で吸入しないと効果がきちんと得られず、声枯れや喉の違和感などの副作用が起こる可能性があります。
吸入治療を始める前に、当院では看護師から吸入方法についての説明を行いますが、ご自身でも動画を見て、理解しておくと良いでしょう。
レルベア・テリルジー吸入方法
シムビコート・パルミコート吸入方法
アドエアディスカス吸入方法
フルティフォーム・オルベスコ・メプチン・アドエアエアー吸入方法
吸入前になるべくのどを潤しておき、吸入後は必ずうがいを忘れずにしましょう。
吸入ステロイドが喉に付着すると、声枯れや喉の違和感、口内炎、口腔内カンジダを招くことがあるためです。外出先でうがいが難しい場合は、吸入後に水を飲むことをおすすめします。
生物学的製剤
吸入ステロイド薬を含む複数の気管支喘息薬を使用してもコントロールが難しい患者様に対して導入しますが、このような患者様は、全体の5~10%程度とされています。
その適応がある患者様においては、専門性を考慮し、当院では大学病院などの高次医療機関へご紹介をさせて頂きます。
アレルギー免疫療法(舌下免疫療法)
アレルゲンを少量から投与して体を慣らし、アレルギー症状を緩和する療法です。
喘息もアレルギー疾患の一種であるため、この療法は有効とされています。
主な効果としては、以下が挙げられます。
- 喘息の発作が減少する
- 治療薬である吸入ステロイドの使用量を減らせる
- 新しいアレルゲン感作を抑える
特に治療を検討すべき喘息の方は以下の通りです。
- アレルギー性鼻炎も合併している方
- 吸入ステロイド治療を行っても喘息のコントロールが難しい方
漢方薬
漢方薬は科学的に有効と証明されているわけではありませんが、吸入ステロイド薬の補完的な役割として処方されることがあります。
実際に、柴朴湯や麦門冬湯が有効であったと報告されています。
また、月経喘息には当帰芍薬散や加味逍遙散が有効であるともされています。
ただし、漫然と使用するのではなく、効果がない場合は服用を中断することが重要です。
定期通院によるモニタリング
生喘息の症状には波があり、外来受診時には症状が軽くなっている患者様も少なくありません。
そのため、普段の状態を正確に理解することが重要です。
外来通院中に、普段の喘息症状が落ち着いているのかをモニタリングする方法としては、以下のようなものが挙げられます。
ピークフローメーター
ピークフローメーターは、ご自宅でも簡単に肺機能検査を行うことができる小型の医療機器です。ピークフローメーターで分かった値(ピークフロー値)は、気道の狭さの程度を示します。
値が低いほど、気道が収縮して発作が起きている状態とされます。
気道の状態を把握するために、毎日ピークフロー値を測定し、喘息日記にピークフロー値、使用した薬、症状を記録することで、患者さまご自身だけでなく医療スタッフにも喘息の状態が把握できるようになります。
これらの情報は治療の参考情報として活用できます。
ピークフローメーターで分かることは以下の通りです。
- ピークフローの値が低くなった場合:発作のサインです。
- 日内変動が大きい場合:状態が不安定で過敏性が強まっています。
- 治療反応性の観察:治療の効果についてチェックできます。
喘息日記
喘息日記には、毎日のピークフロー値、日々の症状、発作の有無を記録していただきます。
外来への受診時には、医師が喘息日記を確認し、今より強い治療を行うのか、減量するかを決定します。
患者様自身も、喘息日記をつけることでご自分の喘息の状態が理解しやすくなります。
発作が起こる前から、対処できるようになります。
喘息治療での最終目標
喘息の患者様においての治療の目標は、咳や喘鳴などの症状がなく、健康な方と同じような日常生活を送ることです。
もし、原因となるアレルゲンがはっきり分かっている場合などであれば、アレルゲンの除去で完治が見込めるケースももちろんあります。
例えば、ネコアレルギーのある方がネコを飼い始めてから喘息を発症した場合、ネコの飼育をやめれば喘息症状はなくなります。
しかし一方で、アレルゲンを見つけるのが困難な場合や、ハウスダストやダニなど環境から100%取り除くことが難しいアレルゲンもあります。
そのような理由により、喘息は完治が難しいことも多いため、薬による副作用を最大→小限に抑えながらコントロールしていくことが大切です。
そのため喘息日記等で普段の状態を医師に報告し、薬の調整や変更についてこまめに相談することが望ましいです。
発作時の治療
喘息の発作が起こった場合、通常の治療だけでなく、吸入気管支拡張薬(短期作用型の吸入β刺激薬:メプチン®)を使用します。
具体的には症状が重くなった時に、メプチンやサルタノールなどの気管支拡張薬を2回吸入します。これは原則1日4回まで可能です。
それでも収まらない場合は、内服用ステロイド薬を3~5日間連続で飲むこともあります。
発作の頻度が多い場合には、次回から定時内服薬を追加する場合もあります。
リモデリング
喘息では、症状が和らいでも気管支の炎症が続いていることが多いです。「症状がないから」といって吸入ステロイドを中断すると、気管支の炎症が悪化する恐れがあります。
炎症が続くと、弾力があって柔らかかった気管支が少しずつ固くなり、治療薬への効果が低下します。この固くなった気管支を「リモデリング」と呼びます。
喘息の患者様の30~50%には常に肺機能の異常があり、一部の患者様ではリモデリングが進んでいることが指摘されています。
特に高齢者ではリモデリングが進行しやすい傾向にあります。吸入ステロイドを2年間続けることで、リモデリングを抑えられることが判明されており、無症状でも吸入ステロイドを続けることの重要性が示されています。
運動誘発性喘息・アスリート喘息
 運動中または運動後に喘息発作が生じることがあります。
運動中または運動後に喘息発作が生じることがあります。
オリンピック選手の中でも8%程度が経験しており、特にマラソンなどの持久競技で多いとされています。
症状は通常の喘息発作と同じように、発作性の咳、息切れ、胸の圧迫感、息苦しさなどが挙げられます。
部活中や体育の時間にこのような症状が出る子供もいます。
運動誘発性喘息は、寒い季節や花粉の時期に起きやすいとされています。
治療方法では、予防的吸入(運動前に気管支拡張薬であるメプチン®を吸入する)方法と、ロイコトリエン拮抗薬の内服が挙げられます。
その他、運動前に10-20分程度の軽いウォーミングアップや、寒冷時にマスクをすることもおすすめできます。
なお、プロのアスリートには、一部の薬剤が投与できません。
使用できる薬でも事前の申請(除外措置申請:TUE)が必要となるため、医師に相談してください。
喘息に良い食事・栄養素
 喘息に良いとされる食事として、まずアレルギーを起こす物質を極力とらない、炎症を抑える栄養素(ω3脂肪酸、抗酸化栄養素)をとる、気管支の平滑筋を緩めるマグネシウムや、免疫を調整するビタミンDを多くとるなどがあります。
喘息に良いとされる食事として、まずアレルギーを起こす物質を極力とらない、炎症を抑える栄養素(ω3脂肪酸、抗酸化栄養素)をとる、気管支の平滑筋を緩めるマグネシウムや、免疫を調整するビタミンDを多くとるなどがあります。
また、喘息の発症には肥満が大きなリスクとなっているため、必要な人は食事内容の見直しとともに、糖質や脂質の多い食事を避け、運動療法を併用し適正体重を目指すことが重要です。
実際に、食事と運動を見直してダイエットを行った結果、喘息のコントロールが改善できたという例も少なくありません。だから、諦めずに共に頑張っていきましょう。