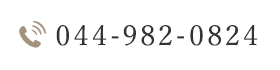- 循環器内科とは
- このような状態になりましたら循環器内科へ受診してください
- 循環器疾患は多くの方がかかる病気
- 循環器内科で行われる検査
- 心筋梗塞によって肩や首、歯、腕が痛くなることも
- 高血圧・脂質異常症と循環器疾患との関係性
循環器内科とは

循環器内科は、心臓と血管の病気を診る診療科です。
「循環器内科」と聞いた時、「重大な病気になった時に行くのかな」というイメージを抱かれる方もいるかもしれません。
しかし、生活習慣病による動脈硬化や足のむくみなども血管障害の1つです。
多くの方が発症する可能性のある慢性症状から、迅速に治療しないと命を落とす重篤な疾患まで、あらゆる症例の診療を実施しています。
このような状態に
なりましたら循環器内科へ
受診してください
心臓の鼓動が速いまたは遅い、脈がとぶ、乱れる、胸(心臓)が痛い、苦しい、背中や左の肩・腕・胸・歯・首が痛い、息が苦しいといった症状は、心臓疾患のサインとして起こっている可能性があります。心拍が乱れる症状は若年層にも起こり得ます。
また、今までこなせていた運動や階段の昇降で息苦しくなる、足のむくみが出るなどの症状も、心臓や血管の異常によって発生することがあります。
こういった症状があるうちに循環器内科へ相談することで、心臓血管系疾患の早期発見、早期治療がしやすくなります。
同じように、高血圧や脂質異常症などの生活習慣病を抱えていて、かつ動脈硬化が心配な場合や、脳血管障害を引き起こす血栓や血管の狭窄・閉塞のリスクを把握したい時にも、精密検査で状態をチェックし、適切な治療へ繋げていくことができます。
循環器疾患は
多くの方がかかる病気
日本では現在「がん」が死因の第1位を、循環器疾患が第2位を占めています。
狭心症や心筋梗塞などの循環器疾患のほとんどは、生活習慣病や加齢に起因する動脈硬化によって起こります。
重篤な疾患を防ぐためには、動脈硬化を発症したばかりの段階から循環器内科へ相談し、心臓や血管の状態をチェックして適切な治療へ繋げることが重要です。
循環器内科で行われる検査
心電図、ホルター心電図
心電図は、心臓の電気活動を記録し、波形の異常から心疾患を見つけたり、心拍のリズムを調べたりする検査です。
不整脈や狭心症、心筋梗塞などの診断に優れており、心拍の乱れを発見するのに用いられます。
ただし、発作が起こった時にしか変化が見られないため、24時間ホルター心電図を用いて1日分の心電図を記録することもあります。
心筋梗塞や心筋症では、心臓の電気活動に異常が起こるため、心電図の波形に異常が見られることがあります。
一方で、弁膜症はある程度進行しないと心電図を行っても異常が見つかりません。
「正常な心電図の波形」=「心臓に病気がない」とは限らない点に注意する必要があり、他の検査と組み合わせて判断することが重要です。
胸部X線検査
一般的には肺の状態をチェックするために行われることが多いですが、心臓や大血管の状態を知るのにも役立ちます。
胸郭に対する心陰影のサイズやうっ血の有無によって心不全などの可能性を考慮することができますし、大動脈の蛇行や動脈硬化で現れる強い石灰化も見つけることができます。
血液検査
心不全時に上昇する脳性ナトリウム利尿ペプチド(NTproBNP」を血液検査で測定できます。}
これは、心室の壁が伸展ストレスを受けたときに分泌され、心不全の重症度に応じて高まるホルモンです。
ただし、腎機能が低下している場合は数値が高く出る傾向があり、肥満の方はそうでない方より低値になることも指摘されています。そのため、データの解釈は慎重に行わなくてはなりません。
慢性心不全の病状変化や治療効果を判定するには、絶対値よりも過去の数値と比べる必要があります。
血圧脈波検査(CAVI:Cardio-Ankle Vascular Index)
これは、大動脈を含む心臓から足首までの動脈硬化を評価する検査で、動脈硬化が進行するほど高い値となります。
一般的に血管が柔らかくしなやかであれば径は変わり、硬いと径はほとんど変わりません。
CAVIは、その時の拡張期/収縮期血圧に対して径がどれだけ変わったかで動脈の硬さを評価します。
PWVと違って血圧の影響をほとんど受けないため、より正確に血管固有の硬さを知ることができます。
同じ性別、同年齢の健康な人の平均と比べることで、血管年齢も出すことができます。
心筋梗塞によって肩や首、歯、腕が痛くなることも
心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患では、突然の胸痛や胸部圧迫感を感じることが多いです。
しかし肩、腕、歯、首などにも痛みが生じることがあり、このような心臓以外に感じる痛みを「放散痛」と呼びます。
「胸と肩」「胸と首」「胸と肩と歯」など、痛む箇所が複数発生することもあります。
心臓の痛みは、体の表面で「ここが痛い」とピンポイントで断言できるものではなく、「この辺」と曖昧な表現になることが多く、人によってはが「胃が痛い」と感じることもあるため、注意が必要です。
さらに、高齢者や糖尿病の方は痛みを感じにくく、典型的な症状が現れない(無痛性心筋梗塞)ことも少なくありません。
高血圧・脂質異常症・糖尿病と循環器疾患との関係性
高血圧、脂質異常症、糖尿病は、動脈硬化と密接に関連しています。
血圧が高いと血管が損傷され、硬くなり柔軟性を失います。
血中にコレステロールが多いと血管にプラークが溜まり、これが狭窄・閉塞を引き起こします。
また、糖尿病による高血糖によっても血管壁が傷つき、血管の内膜に炎症がおこり、そこにコレステロールがつきやすくなり、動脈硬化が進行します。
さらに、プラークが破裂すると血栓が形成され、それが血流に乗って詰まり、心筋梗塞や脳卒中へ至るリスクも高くなります。
血圧や脂質、血糖の数値だけでは把握しきれない血管の状態を詳しく調べることは、これら深刻な疾患の予防に重要とも言えるのです。