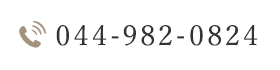咳が止まらない
 咳には風邪による軽い咳から他の病気が疑われる咳まで幅広くあり、お悩みの方も多いです。
咳には風邪による軽い咳から他の病気が疑われる咳まで幅広くあり、お悩みの方も多いです。
咳は1回するごとに2キロカロリー消費すると言われており、3~4回咳をするだけで一曲歌うのと同じくらい、10回咳をすると10分間散歩するのと同じくらいの体力が使われます。
さらに、咳は他の方に感染をうつす恐れもあり周りに気を使ってしまいます。
咳でお困りの方は、
「咳はなぜ出るのか?」
「咳にはどんな種類があるのか?」
「咳を止めるにはどうすればいいのか?」
など、様々な疑問を抱えていると思います。
ここでは、咳が出る原因をメインに、止まらない咳について解説していきます。
「たかが咳」と思われる方もいるかもしれませんが、咳を軽視するのは禁物です。
咳のメカニズム
咳は、空気の通り道(上気道、下気道)に異物や刺激が入り、それを体の外に追い出そうとする防御反応です。
喉や気管支、肺などに異物や刺激があると、受容体(センサー)が異常を感知し、脳の咳中枢に信号を送ります。
脳はその信号を受け取り、呼吸筋や横隔膜に指令を出して咳を促します。
この一連の流れを「咳反射」と呼びます。反射とは、特定の刺激に対して無意識に反応する動きです。
つまり、意識しても反射を止めることはできません。
このような咳反射が起きる理由は、息の通り道に異常があることを知らせる警報器としての役割と、炎症や異物を取り除く消火器としての役割を担っているためです。
咳が起こる原因
息の通り道は2つあり、上気道と下気道に分かれています。上気道には咽頭や喉頭、声帯が含まれ、一般的に喉と呼ばれる部分です。
下気道には、気管支や肺があります。
上気道が原因の咳としては以下のものがあります。
- 咽頭炎・喉頭炎: 喉に菌やウィルスがいることで、それを外に排出しようとする咳です。
- 後鼻漏: 鼻水が上から落ちて喉に張り付くことで、外に排出しようとする咳です。
- 声帯や喉頭部ポリープ: 異物が刺激となり、咳が続きます。
- 逆流性食道炎: 胃液が逆流したことで喉が傷つき、それが刺激となって出た咳です。
下気道が原因の咳としては以下のものがあります。
| 気管支炎・肺炎 | 気管支や肺に菌が侵入しており、それを外に出そうとする咳 |
|---|---|
| 気管支喘息・咳喘息 | アレルギーなどから生じる慢性炎症が刺激となって出る |
| 肺気腫(COPD) | 煙草の煙で気管支や肺が傷つくことで咳が出る病気。 |
| 肺がん | 気管支や肺をがんが圧排し、それが刺激になって咳が出る |
| 心不全 | 気管支や肺が浮腫むことで咳が出る |
| 間質性肺炎 | 様々な炎症が肺の間質を破壊し、咳が出る病気 |
咳には他にも多くの原因があります。上気道といっても、鼻水が喉に落ちたり胃液が逆流したりと、様々な刺激が原因になります。
下気道も、風邪による気管支炎からアレルギーによる気管支喘息をはじめ、肺がんや間質性肺炎などのような重い病気まで、原因は多岐にわたります。
患者様に「どこから咳が出る?」と聞くと「喉から」や「胸から」と実感を述べる方が多いです。
このように、咳には1つの原因がなく、呼吸器内科医はどのような疾患が考えられるかを問診や検査から絞り込み、治療を行います。
咳の種類について
止まらない咳にはいくつかの種類があります。大きく分けて、以下の2つがあります。
- 急に出てきて非常に激しく、生活が困難になる咳
- なかなか治らず、数週間から数ヶ月続く咳
実は、この2つの咳は全く異なるものとして呼吸器内科では考えられます。
咳は持続時間によって以下のように分類されます。
- 3週間以内の咳:急性咳嗽
- 3週間以上8週未満続く咳:遷延性咳嗽
- 8週間以上続く咳:慢性咳嗽
急性咳嗽の原因としては、
- 3週間以内の咳:急性咳嗽
- 3週間以上8週未満続く咳:遷延性咳嗽
- 8週間以上続く咳:慢性咳嗽
感染症が主に考えられます。一方、持続する慢性咳嗽は
など、感染症以外の原因が疑われることが多いです。
感染症であっても、マイコプラズマや百日咳などの特殊な感染症や、結核など周囲に感染するリスクが高い病気を考慮する必要があります。
咳が出る際に痰が出るかどうかも重要な所見です。痰も異物として咳とともに体外に排出されます。
咳が出る際に痰が出るかどうかも重要な所見です。痰も異物として咳とともに体外に排出されます。
- 痰を伴う咳:湿性咳嗽
- 痰を伴わない咳:乾性咳嗽
と呼びます。
湿性咳嗽の代表的な病気には、
- 後鼻漏
- 気管支炎
- 肺炎
などが挙げられます。
一方、乾性咳嗽の代表的な病気には、
- 逆流性食道炎
- 喉頭や声帯ポリープ
- 間質性肺炎
などがあります。
患者様の情報から病気を絞り込むことができますが、必ずしも1つの原因に決めることはできません。
感染症でもマイコプラズマ肺炎や百日咳のように痰を伴わないものもありますし、後鼻漏と気管支喘息や咳喘息が合併していることもあります。
様々な可能性に考慮しながら、咳の原因を探ることが重要です。
止まらない咳の治療方法
 市販薬やよく処方される咳止めは、作用の違いこそあれ、主に気管支や肺の受容体や脳の咳中枢にアプローチして、咳反射をコントロールする薬です。
市販薬やよく処方される咳止めは、作用の違いこそあれ、主に気管支や肺の受容体や脳の咳中枢にアプローチして、咳反射をコントロールする薬です。
「咳が出ているけど、その原因が特定できないままオフにする」という治療とも言えます。
咳止めは、全ての咳の原因に効果がある万能薬ではなく、あくまで症状を一時的に抑えるものです。
そのため、咳が出たらすぐに咳止めを使うという考え方が本当に良いかどうかは再考する必要があります。
重要なのは、急性咳嗽か慢性咳嗽かを区別することです。
急に出てきた激しい急性咳嗽の多くは、菌やウィルスによるものです。
そのため、激しい咳の場合、検査よりもまず応急処置として咳止めを使うのはやむを得ないこともあります。
一方、問題となるのは慢性咳嗽で咳止めを飲み続けることです。これは咳の原因が分からないまま、咳そのものを消し続けるようなものです。
慢性咳嗽は、感染症以外の病気も考慮する必要があります。
気管支喘息や咳喘息などのアレルギー疾患は、アレルギーの炎症を抑える薬が必要で、逆流性食道炎は、胃液を抑える薬が必要です。
さらに、肺癌や結核、間質性肺炎などの命に関わる病気も考慮する必要があります。
このように、慢性咳嗽は原因に応じて多岐にわたる治療が必要で、場合によっては重症化してしまうこともあるので、できるだけ呼吸器内科の受診をお勧めします。
問診と検査を通じて病態を特定し、治療することで咳の原因を根本的に解決することができます。