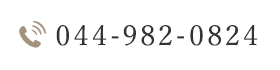糖尿病について

糖尿病は、インスリンが正常に働かない状態で血液中に含まれるブドウ糖の量が増えてしまう病気です。
インスリンは、膵臓から分泌されるホルモンで、血中の糖を細胞内に取り込むことで血糖値を下げる役割を担っています。
糖尿病には大きく2種類あり、免疫の異常などの原因によってインスリンを分泌する膵臓の細胞が破壊されて発症する1型と、主に生活習慣によってインスリン抵抗性が生じて発症する2型があります。
これを放置すると、動脈硬化が進行し、糖尿病の合併症として腎障害、末梢神経障害、網膜症、壊疽などが発生する可能性が高くなり、心筋梗塞や脳卒中などの重篤な疾患のリスクも上昇します。
糖尿病の自覚症状としては、疲れやすさや異常な喉の渇きがよく知られていますが、実際には自覚症状はほとんど現れないことが多いです。そのため健康診断をきっかけに糖尿病が発見されるケースが一般的には少なくありません。
糖尿病内科とは
糖尿病患者は年々増加しており、今や「国民病」とされています。
日本では、2型糖尿病が糖尿病全体の95%を占めていると報告されていますが、症状が現れない期間が長く続くため、治療せずに進行してしまい、合併症に悩む方も少なくありません。
当院では、適切なコントロールによって合併症の発症を防ぐことを目指しています。患者様それぞれの病状に合った治療方針を見つけ出し、一人ひとりのライフスタイルに寄り添った治療プランを進めていきます。
当院の治療法
糖尿病の治療には、以下の3点を意識することが重要です。
- バランスの取れた食事と栄養素
- 適度な運動習慣
- 患者様に合った薬物療法
当院では、患者様の生活習慣や身体の状態を考慮し、適した食事や必要に応じて栄養素の補充、運動習慣を提案します。
また、薬物療法が必要な場合は、注射薬や飲み薬などから適切なものを処方します。
糖尿病に伴う合併症の評価
糖尿病の初期段階では、健康診断で尿中の糖や高血糖を指摘される程度で、明確な自覚症状が現れない傾向があります。
しかし、この状態を長期間そのままにしていると、慢性的な高血糖により全身の血管へのダメージが大きくなり、あらゆる合併症を引き起こすリスクが高まります。
三大合併症
全身の毛細血管に負担がかかることが原因で起こります。ただし、初期段階では自覚症状がはっきりと現れないため、こまめに検査を受けることが重要です。
神経障害
三大合併症の中で最も早く現れるのが末梢神経障害です。これにより、火傷や怪我の痛みを感じない、手足の痺れや違和感といった症状が現れます。
また、胃腸の不調、筋肉の萎縮、筋力低下、立ちくらみ、発汗の異常などの自律神経障害が起こるケースもあります。
網膜症
眼球内の網膜の血管に異常が生じると、浮腫や眼底出血が発生します。初期段階では視覚に異常が起こらず、眼底検査をきっかけに発見される方が多いです。
視覚に異常がなくても、眼科で定期的に眼底検査を受けて、早期発見と早期治療により失明を予防することが大切です。
網膜症は、日本における失明原因の第2位であり、緑内障に次いで多いです。また、白内障の発症リスクを高める要因ともされています。
腎症
腎臓は糸球体という細い血管でできている小さな濾過装置が沢山あつまっていて、老廃物を尿に排出して必要な物質を再吸収する働きをしている臓器です。高血糖が続いて細い血管が傷つき、糸球体が壊れて腎障害が進むと、尿中に蛋白が流れ出てきます。
そのため、糖尿病性腎症を見つけるには、尿検査で蛋白の流出をチェックし、血液検査で腎機能の状態を調べる必要があります。
腎症が進行すると、腎機能が低下して腎不全に至り、透析治療を余儀なくされることもあります。
人工透析導入の原因として最も多いのは糖尿病腎症で、全体の4割を占めています。
その他合併症について
心筋梗塞や脳卒中、脳梗塞をはじめ、感染症や皮膚病、下肢閉塞性動脈硬化症などが挙げられます。当院では、心電図、CAVI(血管年齢測定)などを必要に応じて行います。
糖尿病の治療方法
治療法は、患者様それぞれの病状に応じて決定されます。特に一番重要視されるのは、食事や運動といった生活習慣の見直しです。
特に食事内容を記録して頂き、その内容や食べ方に改善の余地がないかを確認させて頂きます。
食事の内容についてアドバイスを行い、必要に応じて不足しがちな栄養素のサプリメントの提案をさせて頂く場合もあります。
また、薬物療法が必要な場合は、病状、ご年齢、生活習慣をお聞きして、適切な方法を選び、必要な方にはインスリン注射やフリースタイルリブレというリアルタイムでの変動がわかる血糖測定器(厳密には皮膚の間質液内のブドウ糖濃度)の検査実施を提案することもあります。
どんな食べ物を食べたり飲んだりしたときにどれだけ血糖値が上がるのか、ということを把握理解するのに非常に有用な検査です。
それによって血糖値スパイクをできるだけ防ぎ、インスリンをなるべく多く出さない食生活を心がけて頂くことが重要です。
糖尿病だけでなく、高血圧や脂質異常症を合併している患者様は、それらの治療も同時に行います。
療養指導
血糖測定方法の説明やインスリン注射、日常生活におけるお悩みをヒアリングし、治療へのモチベーションを維持できるよう尽力します。
- インスリンを自己注射する方法
- 血糖の自己測定
- 日常生活での注意事項
- 低血糖に関する説明
- その他、生活に関するお悩み相談
など
HbA1c値が高いと
指摘された方へ
糖尿病のリスクをチェックするために、血液検査でHbA1c(ヘモグロビン・エー・ワン・シー)という検査が実施されます。血糖値は運動や食事によって変動しますが、HbA1cはブドウ糖とヘモグロビンの結合割合を調べる検査なので、直近1〜2ヶ月間の血糖値の平均を確かめることが可能です。
HbA1cの値が高い場合、直近1〜2ヶ月間の血糖値も高かったことが疑われます。
特定保健指導における基準値は「5.6%未満」です。HbA1cが6.5%以上だった場合は糖尿病の可能性が高いですが空腹時や随時の血糖値と合わせて判断します。
また、HbA1cが7.0%以上の状態が続いた場合は、合併症のリスクも高まるため、早めに適切な治療を受ける必要があります。
HbA1c値と合併症
HbA1cが高い状態は、「血管に負荷が常にかかっている」サインでもあります。糖尿病の三大合併症(糖尿病性腎症、糖尿病網膜症、糖尿病性神経障害などの細小血管障害)をはじめ、動脈硬化によって発症する心筋梗塞、脳梗塞、狭心症、閉塞性動脈硬化症などの大血管障害のリスクも上昇します。
特に、糖尿病性足病変(足に潰瘍ができる)、認知症、歯周病などは糖尿病によって悪化するリスクが上昇するとされています。これらの病気の発症・進行を予防するためにも、血糖値を適切にコントロールすることが重要です。
また、HBA1cが高くなる原因は糖尿病とは限りません。頻度は少ないですが甲状腺機能亢進症、異常ヘモグロビン症、腎不全などによってHbA1cの値が高くなることもあります。
HbA1cの値が正常でないと確認できた段階から速やかに受診し、早期発見・早期治療を目指していきましょう。