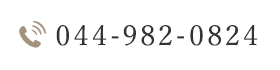乾いた咳が続く
乾いた咳(乾性咳嗽)
コンコン、ケンケンという乾いた咳が特徴です。この咳自体が苦痛を伴うため、咳を抑える治療も必要となります。
主な原因疾患は、アトピー咳嗽、咳喘息、気管支喘息、胃食道逆流症、喉頭アレルギー、間質性肺炎、気管支結核、または降圧薬(ACE阻害剤)の服用などが挙げられます。
痰が絡む咳(湿性咳嗽)
痰が絡んで湿っている、すっきりとしない咳です。
痰による気道粘膜の過剰分泌の治療を行います。
主な原因疾患は、慢性副鼻腔炎(蓄膿症)、慢性気管支炎、気管支拡張症、気管支喘息、肺がんなどが挙げられます。
長引く咳が起こる原因や症状、特徴
感染後咳嗽(かぜ、気管支炎などの後に咳が続く)
- 喉の痛みや鼻水、発熱等の風邪症状後に出る
- 軽い風邪に伴い3週間以上咳が続く
風邪や新型コロナウイルス感染症、マイコプラズマ気管支炎などに罹患した後、咳だけが長引くケースです。
これは気道粘膜が完全に回復せず、わずかな刺激でも咳が出やすい状態になっているためです。
多くの場合、時間の経過とともに自然に改善しますが、必要に応じて鎮咳薬などが処方されることもあります。
副鼻腔炎・後鼻漏
- 鼻水が喉に流れる
- 喉がゴロゴロする
副鼻腔炎の症状の一つに後鼻漏があります。これは、鼻汁が喉の方へ流れ込み、不快感を引き起こす状態です。
その他にも、鼻詰まり、頭の重さ、顔面の痛み、嗅覚の低下といった症状が現れることがあります。
軽度のものなら内服薬で当院でも治療可能ですが、重度の副鼻腔炎や後鼻漏が疑われる場合には、耳鼻咽喉科の受診をお勧めする場合もあります。
逆流性食道炎
- 胸焼け
- 口が苦くなる
- 食後になると咳が出る
- 横になると咳が出る
- 喉が焼ける
胃液や内容物が逆流することで起こる疾患です。喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)を合併するケースも少なくありません。
発症の原因には、食生活の欧米化、塩分摂取量の減少、ピロリ菌感染率の低下などが挙げられています。
また、前かがみの姿勢や締め付けの強い服装、肥満、食道裂孔ヘルニアなども逆流性食道炎のリスクを高める要因とされています。
治療には、H2ブロッカー(ガスターⓇなど)やプロトンポンプ阻害薬(ネキシウムⓇ、タケプロンⓇなど)といった胃酸分泌抑制薬を使用し、胃酸の分泌を抑えます。
また、必要に応じて胃カメラ検査を実施するので、その際には、提携している専門医療機関をご紹介いたします。
肺炎
- 38度以上の発熱がある
- 黄色や緑色の痰が絡んだ咳が出る
- 息切れがする
- 胸痛
この疾患は、細菌やウイルスなどの感染、膠原病といった自己免疫疾患、薬剤、アレルギー、職業性粉塵など、さまざまな原因で発症します。
発熱や痰の状態といった問診のほか、胸部X線検査や胸部CT検査を行い、原因を特定し適切な治療を行うことが重要です。
肺がん
- 血痰
- 咳に痰が絡む
- 動悸や胸の痛みがある
- ダイエットをしていないのに体重が減る
肺や気管支の細胞から発生する悪性腫瘍は「原発性肺癌」と呼ばれ、大腸癌など他の部位から肺に転移した癌は「転移性肺癌」と分類されます。悪性腫瘍は、良性腫瘍と異なり、正常な組織に浸潤して破壊しながら増殖・転移する特徴があります。
肺癌には、肺腺癌、小細胞肺癌、肺扁平上皮癌、大細胞癌など、さまざまな種類があり、診断時の進行度も早期から末期まで幅広く、全身への影響や治療方針は異なります。早期発見された肺癌では治療の選択肢が多く、早期発見と治療が重要です。
結核
- 血痰
- 咳に痰が絡む
- 発熱している
- 息苦しい
- 身体がだるい
結核は、結核菌が肺や気管支に感染することで発症する病気です。結核菌が肺胞に到達し増殖することで、約10~23%のケースで肺結核を発症します。
糖尿病、がん、低栄養状態の方や、免疫抑制剤・副腎皮質ステロイド・生物学的製剤を使用している方、胃を切除した方、HIV感染者など、免疫力が低下している方は発症しやすいとされています。
主な症状としては、2週間以上続く慢性的な咳、体重減少、倦怠感などがありますが、症状が乏しい場合もあり、発見や治療が遅れることも珍しくありません。
診断には、胸部X線検査やCT検査、喀痰検査、インターフェロンガンマを測定する血液検査(IGRA)を用います。
結核菌を排菌している場合は、人から人へ感染する可能性があるため、入院治療が必要となります。
治療は、基本的に複数の抗菌薬を使用し、6ヶ月間にわたって行われます。
咳喘息・気管支喘息
- 夜中から明け方の間に咳が出る
- 風邪を引いた後、咳症状が治らない
- アレルギー性鼻炎を合併している
- アレルギー体質の人が家族にいる
- 喘鳴
気道に慢性的な炎症が生じることで、さまざまな刺激に対して気道が過敏になり、発作的に狭くなることを繰り返す病気です。
埃、タバコの煙、ストレス、ペットの毛などが原因となるほか、夜間から明け方にかけて症状が悪化しやすいのが特徴です。
また、鎮痛剤の使用(アスピリン喘息)や運動後(運動誘発性喘息)に発作が起きることもあります。
発作時には「ヒューヒュー」「ゼーゼー」といった喘鳴(呼吸音)や呼吸困難が生じる場合があります。
発作がない時でも気道には常に炎症が存在し、軽度の症状では乾いた咳のみが現れることもあります。
診断には、採血、胸部X線検査、呼気NO検査などを組み合わせ、総合的に判断します。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 痰を伴う咳が続く
- 階段を上がる等の運動で、息切れや動悸がする
- 40歳以上で喫煙歴が長い
- 症状が進行すると、息を吸うよりも、吐く事につらさを感じる
- 喘鳴
「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」は、主にタバコの煙などの有害物質を長期間吸入することで肺に炎症が生じ、肺気腫や慢性気管支炎を伴う病気の総称です。
COPD患者の約9割は喫煙者とされており、発症リスクは喫煙開始年齢、喫煙本数、喫煙年数といった喫煙量に比例して高まります。
主な症状には、咳、痰、そして身体を動かした際の息切れ(労作時呼吸困難)が挙げられます。息切れは誰にでも起こるものですが、階段を上る、少し速いペースで歩くといった軽い運動で生じる場合は注意が必要です。
診断には、呼吸機能検査、胸部X線検査、CT検査などを行います。
アトピー咳嗽(アレルギー)
- 夕方から夜の間に咳が出る
- 喉がイガイガする
- アレルギー性鼻炎を発症している
- 会話の途中や緊張すると咳が出る
この病気は、気管壁の表層にある咳受容体の感受性が亢進することで咳が引き起こされます。
特徴として、喘鳴を伴わない乾いた咳が3週間以上続き、特に夕方から夜にかけて喉のイガイガ感が現れます。
また、会話中や緊張などのストレスによって咳が誘発されることがあります。
名前の通りアレルギーが関与している咳であり、咳喘息との鑑別が難しい場合もありますが、気管支拡張薬が効果を示さない点が咳喘息との違いです。
治療には抗ヒスタミン薬を使用しますが、その有効率は約6割とされており、有効性が不十分な場合は、吸入ステロイドを併用することもあります。
咳が続く場合の対処法
腹式呼吸を行う
息を吸った時にお腹を膨らませ、吐く時に凹ませる「腹式呼吸」を習慣にすると呼吸が楽になります。
腹筋が弱い方等は慣れていないため、普段から練習しておきましょう。
息を吸う際に口をとがらせる
加湿器の使用や濡らしたタオルを干す、マスクを湿らせる事で湿度を上げます。
こうする事で喉の痛みや違和感が解消されます。
部屋の湿度をあげる
加湿器の使用や濡らしたタオルを干す、マスクを湿らせる事で湿度を上げます。
こうする事で喉の痛みや違和感が解消されます。
水分補給
痰の粘り気を弱くする事で、吐き出しやすくします。また喉の痛みや違和感が解消されます。
市販薬を使用する
市販薬を使用し改善されても、されなくても後日クリニックへ受診してください。
禁煙
喫煙は喉の炎症を進行させるため、禁煙を推奨します。
アルコールを制限する
飲酒によって体内の水分が減り、痰の粘り気が強くなります。アルコールの摂取も減らしましょう。
適度な運動を習慣にする
有酸素運動を行う事で肺機能が高くなります。そうすると症状が起きにくくなります。
咳が続く場合の受診の目安
 咳症状があるからといって、必ずクリニックへの受診が必要というわけではありません。
咳症状があるからといって、必ずクリニックへの受診が必要というわけではありません。
しかし不安な方はお気軽にクリニックを受診してください。
咳が止まらない場合当院で行う検査
胸部レントゲン検査
 肺や心臓に異常がないか確認します。
肺や心臓に異常がないか確認します。
胸部CT検査
 多くの疾患の早期発見が可能です。
多くの疾患の早期発見が可能です。
(例:肺がん、肺結核、気管支拡張症、気胸、胸部大動脈瘤、肺動静脈瘻、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、心臓疾患など)
呼気一酸化窒素検査(FeNO)
呼気中の一酸化窒素(NO)濃度を測定する検査です。
気管支喘息では、気道に常に炎症(特に好酸球性炎症)が生じており、気道上皮で誘導型一酸化窒素合成酵素(iNOS)が増加します。
このため、呼気中のNO濃度を測定することで、気管支喘息による気道の炎症の程度を把握することができます。
また、この検査は喘息治療の効果を評価する際にも有効です。
血液検査
 アレルギーが疑われる場合は、血液検査でアレルギーの種類と有無を確認します。
アレルギーが疑われる場合は、血液検査でアレルギーの種類と有無を確認します。