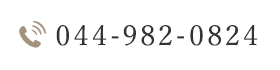花粉症について
花粉症は植物の花粉が原因で引き起こされるアレルギー性鼻炎の一種です。主な症状には以下が含まれます。
- 鼻水
- 鼻づまり
- 頻繁なくしゃみ
- 目のかゆみやゴロゴロとした不快感、充血、涙目
症状が悪化すると、以下のような症状が現れ、日常生活に支障をきたすことがあります。
- 咳やのどの痛み
- 皮膚のかゆみ
- 頭痛
- だるさ
- 不眠
- イライラ感
これらは風邪やインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の症状と似ています。
花粉症の原因となる植物には、スギやヒノキ、シラカンバやハンノキ属(カバノキ科)、カモガヤ、イネ、ブタクサ、ヨモギ属(キク科)などが挙げられます。
これらの植物の花粉が飛ぶ時期に症状が現れやすいため、「季節性アレルギー性鼻炎」とも呼ばれています。
現在、日本人の約38.8%がスギに対してアレルギー反応を持つとされています。
花粉症の検査と診断について
花粉症はアレルギー性疾患の一種です。主な原因はスギやヒノキですが、以下のようなケースもあります。
- 他の植物の花粉に対してアレルギー反応を起こしている場合
- 複数の植物花粉に対してアレルギーを持っている場合
- 花粉症のピーク時期以外に育つ、植物の花粉に対してアレルギー反応が起こっている場合
上記の花粉症を治療するためには、血液検査を行い、各種アレルゲンの調査を実施する必要があります。
血液検査
 血中のIgEの合計数値を調べる「血清総IgE定量検査」に加え、花粉に反応する特定のIgEを測定する「血清特異的IgE抗体検査(RAST検査、MAST検査)」を行います。
血中のIgEの合計数値を調べる「血清総IgE定量検査」に加え、花粉に反応する特定のIgEを測定する「血清特異的IgE抗体検査(RAST検査、MAST検査)」を行います。
これらの検査を行うことで、アレルギーの原因となる植物を正確に見つけます。
一度の血液検査で39種類のアレルギーを調べられる「Viewアレルギー39検査(保険適用)」では、スギやヒノキ、ハンノキ、カモガヤ、ヨモギ、ブタクサ、オオアワガエリなどに対するアレルギーの有無を確認できます。
この検査は花粉だけでなく、ダニやハウスダスト、イヌ、ネコ、カビ、食品などの主要アレルゲンも特定できるため、アトピー性皮膚炎や喘息、アレルギー性鼻炎の患者様にも広く利用されています。
花粉症の治療を始めるタイミング
 花粉症の治療は、開始時期が非常に重要です。
花粉症の治療は、開始時期が非常に重要です。
そのため、花粉の飛散シーズンやピークが来る前に、できるだけ早く当院へお越しください。
飛散シーズンのおよそ2週間前から治療を開始することで、比較的軽い症状でピーク時を乗り越えることができます。ただし、状況によっては即効性の高い治療も選択できます。
花粉症と風邪の違い
| 花粉症 | 風邪 | |
| 症状が出る期間 | 飛散する時期 | 1日~数日のうちに解消される |
| 鼻水の特徴 | 水っぽくサラサラしている。透明色。 | 粘度がある。色は白または黄色に近い。 |
| 発熱の有無 | 発熱はあまり出ない。 出たとしても微熱程度で済む。 |
高い熱を出すことがある。 |
| 喉 | 違和感がある程度 | 強い腫れや痛みが出る。 |
| 頭痛 | あっても軽く済む | 強い頭痛が現れることもある。 |
| 咳や痰 | 患者様によっては現れることもある。 | よく見られる |
花粉症と風邪の症状は非常に似ているため、見極めは難しいです。
初期症状や段階によっては判断するのが難しいため、お悩みの際はご相談ください。
治療方法
 特に花粉が飛散する2週間前から抗ヒスタミン剤(アレグラなど)の内服薬薬を用いることで、早期に効果を発揮できます。
特に花粉が飛散する2週間前から抗ヒスタミン剤(アレグラなど)の内服薬薬を用いることで、早期に効果を発揮できます。
スギ花粉の治療を実施する場合は、花粉症シーズンの約1ヶ月前から抗ヒスタミン薬の服用を開始します。
これにより、ヒスタミンの放出を抑え、発症を遅らせたり症状を軽くしたりすることが可能です。
鼻の症状が重い方には点鼻薬を、目の症状が目立つ方には点眼薬も併せてお出しします。
抗ヒスタミン薬の副作用として「強い眠気」がよく指摘されますが、最初から比較的眠気が出にくい抗ヒスタミン薬や漢方薬を選択することも可能です。
その際はお気軽にお申し出ください。
日頃からできる対策について
花粉症は一度でも発症すると、花粉の量に応じて毎年症状が現れます。最も有効な対策は、「花粉が飛散するシーズン前から治療すること」です。
また、花粉に触れる機会をできるだけ減らすことも重要です。具体的な対策としては、以下の方法があります。
- 髪の毛や目、鼻、口の中などに花粉が付かないよう、マスクや眼鏡、帽子などを活用する
- 上着などに付いた花粉を払い落としてから家に入る
- 手洗いやうがいをこまめに行う
- 定期的に掃除をする
- 空気清浄機を活用する
- 洗濯物は室内で干す
- 栄養バランスの整った食事を心がける
- 適度な睡眠時間を確保する
- ストレスは上手に昇華させる
- アレルギー反応を軽減するために腸内環境を整える。
- 免疫を整えるビタミンDを多くとる。
これらの対策を実践し、生活習慣を見直して、できるだけ花粉から遠ざけた生活を心がけましょう。