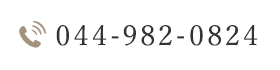血圧について

心臓から送られた血液が、血管の壁を押す力を「血圧」と言います。
血液は心臓が収縮する際に勢いよく送り出されます。
心臓が収縮している際の高い血圧を「収縮期血圧」、心臓が拡張している時の低い血圧を「拡張期血圧」と呼びます。
血圧計で測定すると、2つの数値が表示されます。
これが収縮期血圧(上の血圧)と拡張期血圧(下の血圧)です。
どこから高血圧になるのか
高血圧の基準は、診察室での収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上、家庭血圧での収縮期血圧が135以上、または拡張期血圧が85以上です。
どれかに該当すると高血圧と診断されます。
高血圧を放置すると、血管に大きな負荷がかかり、動脈硬化のリスクが高まります。動脈硬化はさらに高血圧を悪化させる原因にもなります。
これらは自覚症状が少ないため、いつの間にか重症化しやすい傾向があります。動脈硬化が進行すると、心筋梗塞や脳卒中のリスクも上昇します。
適切な診断と継続的な治療を受けることで、これらのリスクを軽減しましょう。
診察室血圧と家庭血圧の違い
血圧は体重と同様に、運動や入浴、ストレス、トイレ、食事などの日常生活の行動で変動します。
そのため、一度の計測だけでは正確に判断することができません。血圧には、「診察室血圧」「家庭血圧」「24時間血圧」の3種類があります。
診察室血圧は、病院などの医療機関で測定する血圧で、家庭血圧とはご自宅内で測定された血圧です。
そして、24時間血圧とは、特殊装置で24時間の変化を測定することで得られた血圧のデータです。
病院での診察室血圧は、緊張によって数値が高くなることが多いです。
一方、家庭血圧は診察室血圧より低くなる傾向がありますが、心筋梗塞や脳卒中などのリスクを判断する重要な要素です。
そのため当院では、高血圧の患者様に対して、ご自宅で継続的に血圧を測り記録することをお勧めしています。
高血圧治療
ガイドラインの内容
『高血圧治療ガイドライン2024』でも、2019年版に引き続き、75歳未満の成人の目標血圧を130/80mmHg未満、75歳以上では140/90mmHg未満と定めています。
糖尿病の患者様や抗血栓薬を服用している方、蛋白尿陽性のCKD患者様の目標血圧は130/80mmHg未満、脳血管障害や蛋白尿陰性のCKD患者様の場合は140/90mmHg未満です(いずれも診察室血圧基準)。
家庭血圧の場合、75歳未満の成人の目標は125/75mmHg未満、75歳以上では135/85mmHg未満です。
糖尿病の患者様や抗血栓薬を服用している方、蛋白尿陽性のCKD患者さんの家庭血圧目標値は125/75mmHg未満、脳血管障害や蛋白尿陰性のCKD患者さんの場合は135/85mmHg未満です。
診断においては、緊張による影響を避けるため、家庭血圧を優先して診断をつけることもあります。
高血圧が起こる原因
 高血圧の90%は本態性高血圧で、遺伝的素因や生活習慣(塩分・油分の過剰摂取、喫煙・飲酒の習慣、肥満、運動不足など)、ストレス、睡眠不足などが引き金と言われています。
高血圧の90%は本態性高血圧で、遺伝的素因や生活習慣(塩分・油分の過剰摂取、喫煙・飲酒の習慣、肥満、運動不足など)、ストレス、睡眠不足などが引き金と言われています。
この高血圧の発症・悪化を予防するには、生活習慣の改善が重要です。
残りの10%は二次性高血圧と言い、ホルモン分泌異常や腎臓疾患などの他の疾患や薬剤の副作用が原因で発症します。
このタイプは、通常の降圧剤では効果がない場合もありますが、原因となる疾患の治療を行うことで血圧を改善することが期待できます。
生活習慣が原因で高血圧になる場合、糖尿病など他の生活習慣病を併発するケースも多く、さらに、肥満体型の方は動脈硬化のリスクが高くなるため、減量を心がけましょう。
高血圧などの生活習慣病は「サイレントキラー」とも呼ばれ、自覚症状が少ないため重症化しやすい傾向があります。
もし健康診断で医師から指摘された場合は、なるべく早めに治療を受けましょう。
高血圧の治療方法
生活習慣の改善には、減塩、減量、禁煙、禁酒(もしくは減酒)、週に3回程度以上の運動が含まれ、必要に応じて薬の処方も行います。
高血圧を改善するには、正常な血圧に戻すための生活習慣を継続することが不可欠です。
患者様の健康状態によっては、治療開始の段階から比較的厳しい食事制限や改善が必要とされる場合もあります。
しかし目標を高く設定しすぎると挫折もしやすいため、精神的にも身体的にも負担が少ないところから始めると良いでしょう。
医師との相談を重ねながら、ご自分に合った改善方法を見つけていきましょう。
生活習慣の見直し
塩分制限
「和食」=「ヘルシー」と思われる方も多いと思いますが、実は塩分摂取量が多い傾向にあります。
そのため、日本人にとって塩分制限は特に有効とされています。
減塩料理に対して「味が薄くなる」や「美味しくなさそう」と感じるかもしれませんが、出汁やトマトなどのアミノ酸を含む食品、香りの強い薬味やスパイスを使うことで、しっかりと風味のある料理を味わえるようになります。
1日の塩分摂取量はできるだけ「6グラム未満」に抑えるようにします。
ハムやベーコンなどの加工肉、チーズ、漬物、インスタント食品には塩分が多く含まれています。
これらを無意識に摂取してしまうと、1日の塩分摂取量が簡単に超えてしまいます。
塩分が多く含まれた食品はできるだけ減らしましょう。
減量・肥満の予防
体重管理を始める前に、まずはご自身の身長から計算した標準体重を知りましょう。
体重が「標準」・「肥満」・「低体重」のどれに該当するかは、BMI(体格指数)を計算することで確認できます。
「肥満」または「低体重」のどちらも疾患発症のリスクが高まります。BMIの計算式は、下記の通りです。
体重(kg)÷{身長(m)×身長(m)}
標準体重のBMIは22、肥満の基準はBMI25以上、低体重はBMI18.5以下です。
標準体重を維持することは、疾患発症のリスクを抑えるために非常に有効なので、まずは標準体重を目標にして、体重をコントロールしていきましょう。
特に肥満は生活習慣病のリスクを高めますが、急激な体重減少は貧血や生理不順(女性の場合)などを起こしやすく、リバウンドのリスクも高まります。そのため、段階的に体重を減らしていくことが重要です。
適度なカロリー制限と運動を組み合わせて、標準体重を目指し、達成後もそれを維持できるライフスタイルを心がけましょう。
減酒・禁酒
以前は1日の適量は、日本酒は「1合まで」、ビールは「500ccまで」となっていました。
しかし最近の研究では、1合未満の少量の飲酒でもリスクが高まる疾患があることがわかっています。
ですので、アルコールは飲まないにこしたことはないわけですが、どうしても飲むなら、せめて基準以内で楽しむようにしましょう。
運動
運動の習慣化は、高血圧を含む生活習慣病の発症・悪化を予防するためにおいて非常に大切です。
軽く汗ばむ程度の運動を1日30分、週に3日以上行う習慣を身につけましょう。
持病がある方は、運動制限が必要な場合があるので、なるべく事前に医師と相談して、指示に従いながら運動を続けましょう。
禁煙
禁煙は高血圧予防にとどまらず、呼吸器疾患の発症や悪化の予防にも有効です。
喫煙は血管を収縮させ、血圧を上昇させてしまうため、禁煙は必ず行いましょう。
喫煙が習慣化すると、減塩やカロリーコントロール、運動などの対策を続けても、十分な効果が得られなくなります。
薬物療法
降圧剤(血圧を下げる薬)の中には、様々な作用機序(薬物が効能を発揮する仕組み)の薬があり、状態によって使い分けられます。
また同じ1つの薬でも、個体差により効果や副作用の現れ方が変わることがあります。
- 血圧の数値
- 年齢
- 体重
- 性別
- 持病がないか
- ライフスタイル
- 服用しやすい薬の形状(錠剤または粉末剤)
診察時には、処方する薬の内容、副作用、服用時の注意点、メリット・デメリットなどを丁寧に説明します。
不明な点や不安がございましたら、遠慮なくお尋ねください。
| 利尿剤 | 尿量を増やすことで血液量を減らし、血圧降下を目指すために処方します。 |
|---|---|
| 血管拡張剤 | 血管を拡張させて血圧を降下させます。 |
| 神経遮断剤 | 血管の緊張や心臓・血管への過剰な刺激を抑え、血圧を降下させます。 |
| レニン・アンギオテンシン系薬 | ホルモンの動きをコントロールして、循環血液量を調整し、血圧を降下させます。 |