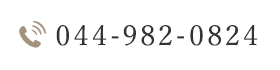内科について

当院は、なんとなく身体の不調を感じたり、どこに相談すれば良いのか分からなくなったりした時に駆け込みやすい、気軽に相談しやすいかかりつけ医を目指しています。
一般内科診療では風邪や生活習慣病に加え、呼吸器、消化器、循環器、血液、感染症、アレルギーなどの診察も行っています。
気になることがありましたら、その疾患に適した専門医へのご紹介にも対応可能です。
どうぞお気軽にご相談ください。
内科でよくある症状
頭痛
頭痛について
一言で頭痛と言っても、沢山の種類の頭痛が実際にはあります。
大きく分けて、繰り返して起こる慢性頭痛症(一次性頭痛)と、脳腫瘍、髄膜炎、脳炎、クモ膜下出血や脳卒中などの脳や頭部の病気の症状として出てくる症候性頭痛(二次性頭痛)があります。
一次性頭痛には、片頭痛、緊張型頭痛、三叉神経・自律神経性頭痛(TACs)、その他ニューロパチーなどがあり、頻度は比較的多いです。
二次性頭痛には、頭頸部外傷による頭痛(例:むち打ち)、くも膜下出血、脳出血、脳腫瘍、高血圧性脳症、椎骨動脈解離、側頭動脈炎、薬剤の使用過多による頭痛、髄膜炎、高山性頭痛、急性副鼻腔炎からくる頭痛または顔面痛、うつ病など精神疾患による頭痛なども含まれます。
頭痛の診断、治療
痛みの様子、症状、頻度、血圧、神経学的所見から診断し、その病態に即した薬物治療や生活指導を開始します。
場合によっては副鼻腔Xpや頭部CTやMRI検査を行ったり、大学病院などの脳神経外科がある専門医療機関にご紹介することもあります。
発熱
発熱について
発熱は、体温が通常よりも高くなる状態を指し、体が感染症や炎症に対抗するための自然な反応です。
発熱は、細菌やウイルスなどの病原体が体内に侵入した際に、免疫系がこれらの外敵と戦うために生じます。
脳の視床下部が体温調節中枢として、体温を上げる指令を出すことにより、体は寒さを感じ、震えたり、布団にくるまったりして体温を上げようとします。
発熱時には、代謝が亢進し、体温が1°C上昇すると代謝が13%増加し、熱感、発汗、倦怠感なども生じます。
発熱がおこる原因
発熱の原因はいろいろありますが、一般的には以下のものが挙げられます。
感染性
バクテリア、ウイルス、真菌、寄生虫などの病原体による感染。
例) インフルエンザ、コロナウィルス、風邪、胃腸炎など
炎症
体内の組織や器官が損傷または刺激を受けた際の免疫反応。
例) リウマチ性関節炎、潰瘍性大腸炎
環境要因
体温調節がうまくいかない場合。
例) 熱中症、過剰な運動
薬剤性
特定の薬剤に対するアレルギー反応や副作用。
例) 抗生物質、抗てんかん薬
免疫系の異常
自己免疫疾患など、免疫系が誤って自分の体を攻撃する場合。
例) 全身性エリテマトーデス、自己免疫性肝炎
その他の疾患
癌、甲状腺機能亢進症など。
例) 白血病、悪性リンパ腫
発熱は、これらの原因によって引き起こされる体の防御機構の一部ですが、熱が続いたり、他の症状が現れたりした場合は、医師に相談することをお勧めします。
咳
咳について
咳は、気道に異物や刺激物が入った際にそれを排除しようとする反射的な反応です。
咳にも種類があり、それぞれに原因があります。
咳の原因
風邪やインフルエンザ、コロナ感染
ウイルス感染によるもので、気道の急性の炎症で、咳や発熱、のどの痛みが主な症状です。
軽症から重症まで幅広い症状が見られ、咳は通常数日から1週間程度続きます。
気管支喘息
気道の慢性的な炎症によるもので、発作的な咳や喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューという音)が特徴です。
特に夜間や早朝に悪化します。
副鼻腔気管支症候群
慢性的な副鼻腔炎が進行し、気道に影響を及ぼすことで発症し、副鼻腔炎と気管支炎が同時にある状態です。
鼻閉、鼻汁、後鼻漏、微熱などが特徴です。
逆流性食道炎
胃酸が食道に逆流し、気道を刺激することで咳が出ます。特に食後や体が横にする時に症状が現れることが多いです。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
主に喫煙が原因で、気道が狭くなり、慢性的な咳と痰が続きます。特に朝方に多く痰を伴うことが特徴です。
咳喘息
喘息の一種で、主な症状が咳のみです。乾いた咳が夜間や早朝に悪化します。
アトピー咳嗽
アレルギー体質のある方に多く見られる慢性的な咳で、乾いた咳が主症状です。
気管支炎
気管支に炎症が生じる病気で、風邪や細菌感染が原因です。咳と痰、発熱が特徴です。
肺炎
ウイルスや細菌による感染症で、咳や痰、発熱が主な症状です。免疫力が低下している人に多いです。
アレルギー性鼻炎
アレルギー反応によるもので、鼻水やくしゃみとともに咳が出ます。
特にアレルゲンが飛散する季節の変わり目に症状が悪化します。
百日咳
百日咳菌による感染症で、発作的な激しい咳が特徴です。特に夜間に悪化し、咳込んだ後に嘔吐を伴うことがあります。
肺結核
結核菌による感染症で、長期間続く咳や痰、微熱が特徴です。進行すると血痰や胸の痛みを伴うことがあります。
肺がん
肺がんの初期症状として咳や痰が出ることがありますが、自覚症状がない場合も多いです。
進行すると血痰や息苦しさが現れることがあります。
心不全
心臓の機能が低下し、肺に液体がたまることで咳が出ます。
特に横になると症状が悪化します。
これらの原因はそれぞれ対処法が異なるため、咳が長引く場合や症状が重い場合には、自己判断だけに頼らず、医療機関での診察を受けることが重要です。
痰
痰について
痰(たん)は、気道や肺から分泌される粘液で、異物や病原菌を排出する役割を持っています。
痰の色や性状によって、原因となる病気や状態をある程度推測することができます。
痰の種類と原因
発熱の原因はいろいろありますが、一般的には以下のものが挙げられます。
透明または白色の痰
気管支喘息、初期の気管支炎、アレルギー性鼻炎など。
細菌性ではない軽度の気道の炎症があることを示します。
黄色の痰
急性喉頭炎、急性扁桃腺炎、急性気管支炎、肺炎など。
ウィルスや細菌感染による炎症がある程度進行していることを示すことが多いです。
緑色の痰
慢性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、気管支拡張症など。
細菌感染がさらに進行し、膿が混じっていることを示すことがあります。
ピンク色または赤色の痰
肺炎、肺結核、肺がん、心不全など。
ピンク色や赤色の痰は、血液が混じっていることを示します。
茶色の痰
喫煙、肺炎、肺がんなど。
茶色の痰は、古い血液やタールが混じっていることを示します。喫煙者や一部の肺炎、肺がんの患者で見られます。
もし痰が続くようなら、重症化する前に一度医療機関にご相談ください。
腹痛
腹痛について
腹痛にはさまざまな種類と原因があり、痛みの種類から大きく、内臓痛、体性痛、関連痛の3つに分かれます。
内臓痛
胃や腸などの内臓が引き伸ばされたり、けいれんしたりすることで生じる痛みです。
部位ははっきりしないことが多く、鈍痛や締め付けられるような痛みが特徴です。
例) 胃炎、胃潰瘍、腸閉塞、胆石など。
体性痛
腹膜や腸管膜、横隔膜などに炎症が波及して生じる痛みです。
鋭い痛みが持続的に続き、痛みの部位がはっきりしています。
例)腹膜炎、虫垂炎、胆嚢炎など。
関連痛
痛みの原因となっている場所とは別の部位で感じる痛みです。
例えば、心臓の痛みが左肩や下顎などの離れた場所に感じられることがあります。
例)心筋梗塞、胆石症など。
腹痛の部位と原因
心窩部痛(みぞおちの痛み)
胃潰瘍、急性胃炎、逆流性食道炎、胆石胆嚢炎、心筋梗塞など。
右上腹部痛
胆石胆嚢炎、十二指腸潰瘍、急性肝炎、胸膜炎など。
左上腹部痛
胃潰瘍、急性膵炎、尿管結石、胸膜炎など。
臍周囲痛(へその周りの痛み)
胃潰瘍、腸閉塞、急性膵炎、腹部大動脈瘤など。
側腹部痛
尿管結石、虚血性腸炎、腎盂腎炎など。
下腹部痛
虫垂炎、大腸憩室炎、急性腸炎、便秘、卵管炎、膀胱炎など。
背部痛
急性膵炎、膵臓がん、尿管結石、腎梗塞、腹部大動脈瘤など。
腹痛の原因は多岐にわたるため、痛みが続く場合や強い痛みがある場合は、医療機関の受診をお勧めします。
吐き気
吐き気について
胃の内容物を吐き出そうとする感覚や欲求のことで、通常は不快感やむかつき、こみ上げるような感覚を伴います。
吐き気の原因はさまざまです。
吐き気の原因
胃腸の問題
急性胃炎、胃潰瘍、逆流性食道炎、感染性胃腸炎など。
感染性
インフルエンザや急性胃腸炎など、ウイルスや細菌の感染症。
薬の副作用
一部の薬、特に抗生物質や鎮痛剤、抗がん剤などによる。
妊娠
妊娠初期の「つわり」として吐き気が起こる。
過度なストレス
精神的な要因で起こる。
内耳の問題
メニエール病や乗り物酔いなどで起こる。
脳の問題
脳腫瘍や脳梗塞、脳出血、頭部外傷、髄膜炎などにより脳圧が亢進して起こる。
心臓の問題
心筋梗塞や心不全などで吐き気が起こることもあり。
嘔吐
嘔吐について
胃の内容物を口から吐き出すことで、脳内の嘔吐中枢が刺激されることで起こります。
嘔吐の原因はさまざまで、対処法も原因によって違います。
嘔吐の原因
胃腸のトラブル
急性胃炎
食べ過ぎや飲み過ぎ、ストレス、アレルギー、ウイルス感染などにより、胃の粘膜が炎症を起こした状態。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
ピロリ菌感染や鎮痛剤の過剰使用が原因で、胃や十二指腸に潰瘍ができることがあります。
感染性
食中毒
腐った食品や毒性のある食品を摂取することで発症する。
ノロウイルスやO157(病原性大腸菌)、黄色ブドウ球菌、カンピロバクターなどが有名です。
急性胃腸炎
ウイルスや細菌の感染が原因で、吐き気、嘔吐、下痢、発熱が主な症状です。
内耳の問題
メニエール病
内耳の異常により、めまいや耳鳴り、吐き気が発生します。
乗り物酔い
乗り物の揺れによる平衡感覚の乱れが原因です。
むくみ
むくみについて
浮腫(ふしゅ)は、体内の組織に過剰な水分が蓄積することによって引き起こされる腫れのことです。
浮腫の原因はさまざまです。
むくみがおこる原因
心機能障害
心臓のポンプ機能が低下すると、血液を全身に送り出すことが難しくなり、血液が滞って毛細血管内圧が上昇します。
その結果、水分が間質に移動し浮腫が生じます。
腎機能障害
腎臓の機能が低下すると、体内の水分やナトリウムの排泄がうまくいかなくなり、浸透圧の関係で浮腫が発生します。
肝機能障害
肝臓の機能が低下すると、血液中のタンパク質(アルブミン)の合成が減少し、血管内の水分を保持する力が弱まり、浮腫が生じます。
リンパ管の障害
リンパ管が圧迫や狭窄、閉塞することで、リンパ液の流れが悪くなり、浮腫が発生します。
他にも座りがちな生活、妊娠、月経前症状などのホルモン関連、特定の薬の副作用なども考えられます。
黄疸
黄疸について
黄疸(おうだん)は、血液中のビリルビンという黄色い色素が増加し、皮膚や目の白い部分が黄色くなる症状です。
黄疸の原因はさまざまです。
黄疸の原因
溶血性貧血
赤血球が過剰に破壊されることでビリルビンが増加し、黄疸が発生します。
肝細胞性黄疸
肝臓の細胞が損傷し、ビリルビンの代謝がうまくいかなくなることで黄疸が生じます。
急性肝炎や肝硬変が代表的です。
閉塞性黄疸
胆道が結石や腫瘍(がん)などで閉塞され、ビリルビンの排泄が妨げられ、発生します。
体質性黄疸
遺伝的にビリルビンの代謝がうまくできず、黄疸が生じることがあります。
息切れ
息切れについて
息切れ(呼吸困難)は、体が必要とする酸素を相対的に十分に取り込めない状態を指します。
息切れの原因はさまざまです。
息切れの原因
肺の病気
肺炎、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などで生じることがあります。
心臓の病気
心不全、心筋梗塞、狭心症などの心臓の病気で息切れが発生することがあります。
貧血
血液中の赤血球が不足すると、酸素を十分に運ぶことができず、息切れが生じます。
肥満
体重が増えると、呼吸器や心臓に負担がかかり、息切れしやすくなります。
運動不足
運動不足によって心肺機能が低下するため、少しの運動でも発生しやすいです。
ストレスや不安
強いストレスや不安などで過呼吸や息切れが生じることがあります。
動悸
動悸について
動悸(どうき)は、心臓が通常よりも速く、強く、または不規則に鼓動する状態のことです。
動悸の原因はさまざまです。
動悸の原因
不整脈
心臓のリズムが乱れることで生じます。心房細動や期外収縮などがあります。
ホルモンの異常
甲状腺機能が過剰に活発になるバセドウ病、副腎髄質に発生してカテコラミンを過剰 に産生する褐色細胞腫などにより、心拍数が増加することがあります。
低血糖
血糖値が低下すると、体がストレス反応で交感神経優位になり、動悸が生じます。
貧血
血液中の赤血球が不足し、通常の心拍数では酸素供給が不十分のため、代償的に心拍 数を上げる作用が働き、動悸が生じます。
気管支喘息
発作時に呼吸困難が生じ、心臓が酸素を供給しようとして動悸が発生します。
心因性
強いストレスや不安が原因で交感神経が優位になり、動悸が発生しやすくなります。
鼻閉
鼻閉について
鼻閉(びへい)は、鼻腔が狭くなり、空気の通りが悪くなる状態です。
鼻閉の原因もさまざまです。
鼻閉の原因
アレルギー性鼻炎
花粉やハウスダストなどのアレルゲンが原因で、鼻粘膜が腫れて生じます。
副鼻腔炎
副鼻腔(鼻の周りの空洞)の炎症が原因で、粘性の高い鼻汁が過剰産生されるために生じます。
慢性副鼻腔炎や急性副鼻腔炎の両方があります。
鼻中隔湾曲症
鼻中隔(鼻の左右を分ける壁)が曲がっているため鼻腔が狭くなり、生じます。
鼻茸(はなたけ)
鼻腔内にできるポリープが原因で、空気の通り道が狭くなるため、起こります。
薬剤性鼻炎
長期間の点鼻薬使用が原因で、鼻粘膜が腫れ、鼻閉が生じることがあります。
頻尿
頻尿について
頻尿(ひんにょう)は、通常よりも頻繁に排尿する状態で、一般的に朝起きてから就寝までの排尿回数が8回以上の場合を言います。
頻尿の原因はさまざまです。
頻尿の原因
過活動膀胱
膀胱が過敏になり、尿が十分に溜まっていないのに強い尿意を感じる状態です。
脳卒中やパーキンソン病などの神経系の病気が原因となることもあります。
尿路感染・炎症
膀胱炎や前立腺炎などの尿路感染が原因で頻尿が生じます。
残尿が起こる疾患
排尿後にも膀胱内に尿が残る状態のため、それを出したい感覚が働き、生じます。
前立腺肥大症や糖尿病、腰部椎間板ヘルニアなどがあります。
多尿が起こる疾患
1日の尿量が増える状態のため、排尿頻度も多くなります。
糖尿病や腎機能低下、水分の多量摂取、利尿剤の使用が原因となります。
心因性
ストレスや不安が原因で交感神経優位になり、頻尿が生じることがあります。
特に緊張する場面でトイレが近くなることが多いです。
糖尿病
糖尿病とは、長期間にわたり血液中の血糖値が高くなる状態です。
これは、血糖値を調節するインスリンの分泌量が低下したり、インスリンが正常に機能しない(インスリン抵抗性)状態が生じるために起こります。
多くは自覚症状がほとんどないまま病気が進行するため、病気の理解が不十分なまま、治療を受けずに過ごしてしまう方も少なくありません。
適切な治療を行わずにいると、高血糖が原因で血管が傷ついて血流も悪くなり、糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害、さらには脳卒中や心筋梗塞などのリスクが高まります。
糖尿病が重症化すると失明や足の切断、人工透析を余儀なくされることもあり、日常生活に大きな影響を及ぼします。
当院では糖尿病に精通した医師が適切な検査と治療を行っています。血糖値で異常を指摘された際は、早めにぜひご相談ください。
脂質異常症
血液中のコレステロールや中性脂肪の数値が高すぎる、もしくは逆に低くなりすぎる状態です。
この数値が高い状態が続くと、自覚症状がないまま動脈硬化が進行し、血管が狭くなったり閉塞したりして、脳梗塞や心筋梗塞を引き起こすリスクを高めます。
飲酒、食べ過ぎ、栄養の偏り、喫煙、運動不足などといった生活習慣により主に発症するため、食事の栄養バランスを整え、節酒、禁煙や運動習慣を取り入れるなど、生活習慣の改善が必要なことが多いです。
しかし、一部には、甲状腺ホルモンの低下や一部の腎疾患によっても起きることがあるので、それも検査確認する場合があります。
また、数値が低すぎる状態も栄養不足や夜間低血糖の可能性等があるため、早期発見のためにも、検査は定期的に受けるように努めましょう。
高血圧
高血圧とは、血管内の圧力が高くなる状態です。ただし、血圧は緊張や温度変化などでも数値が変動しやすいという特徴を持っています。
診察室での計測で140/90mmHg以上、家庭血圧で135/85mmHg以上が高血圧と診断されます。
長期間高血圧が続くと、動脈硬化が進行し、脳梗塞、脳卒中、心筋梗塞、狭心症、腎臓病などのリスクが高まり、心機能低下による心不全のリスクも伴うようになります。
治療には、食生活の改善や塩分制限、運動による減量、睡眠の改善などの生活習慣の見直し、ストレスの緩和などが重要です。
これらの改善が効果を示さない場合は、薬物療法を検討します。
適切な治療を行い、正常な血圧値を目指しましょう。
高尿酸血症(痛風)
これは血液中に尿酸という代謝物がが多くなった状態のことです。
尿酸が血液内で溶けきれなくなると尿酸結晶が形成され、足の親指の付け根や関節内に蓄積し、痛風を引き起こします。
これにより、激痛や腫れ、発赤が生じ、いわゆる「風が吹いても痛い」という状態になります。
また高尿酸血症の方は尿が酸性に傾くことが多いため、腎臓や尿管、膀胱などの尿路で結晶化して尿路結石になりやすくなります。
尿酸値が高くなる原因の1つとして、プリン体の大量摂取が挙げられます。ビール、レバー、魚卵、イワシ、カツオ、海老、干し椎茸などにはプリン体が多く含まれているため、これらの食品の摂取量には注意が必要です。
治療としては、生活習慣の改善と薬物療法が挙げられます。
節酒、食習慣の改善、摂取カロリーの制限、適度な運動による減量を行いますが、コントロールが難しい場合には、主に尿酸生成阻害薬を併用します。
しかし痛風発作が起きてしまった急性期には、非ステロイド抗炎症薬などをまず使い、炎症が収まってから上記の薬を開始または再開します。
痛風発作が繰り返される場合には、発作の前兆を感じたときに飲む予防薬を使用し、痛風発作や痛風関節炎の予防を目指します。
花粉症
花粉症は、春や秋など花粉が飛散する時期に発症する病気です。
春にはスギやヒノキ、秋にはブタクサなどの花粉(アレルゲン)が飛散します。
症状としては、鼻水、充血、涙目、皮膚のかゆみ、倦怠感、微熱、不眠などが挙げられ、ひどくなるとると日常生活に大きな影響を及ぼします。
当院ではアレルギー検査を実施するだけでなく、舌下免疫療法にも対応しています。
花粉が飛散するシーズンでも快適に過ごせるよう、早いうちに適切な治療を受けることをお勧めします。
感冒
感冒について
感冒(かんぼう)、一般的には風邪(かぜ)と呼ばれる病気は、上気道(鼻や喉)の急性炎症の総称です。
風邪の主な原因はウイルス感染であり、200種類以上のウイルスが関与していると言われています。
感冒の原因
ウイルス感染: 風邪の原因の約90%はウイルスによるもので、ライノウイルス、RSウイルス、アデノウイルスなどが含まれます。
症状
くしゃみ、鼻水、鼻づまり喉の痛み、咳、痰、発熱、頭痛、筋肉痛、関節痛、全身倦怠感などが現れます。
症状の表れ方は、ウィルスの種類によっても違い、また個人差もあります。
膀胱炎
膀胱炎について
膀胱炎(ぼうこうえん)は、膀胱の粘膜が炎症を起こす病気で、主に細菌感染が原因で発生します。
膀胱炎の原因
細菌感染
大腸菌などの細菌が尿道を通じて膀胱に侵入し、感染を引き起こすものです。
特に女性は男性に比べて尿道が短いため、感染しやすい傾向があります。
尿道カテーテル
長期間のカテーテル使用が原因で、細菌が膀胱に侵入しやすくなります。
免疫力の低下
免疫力が低下すると、細菌感染に対する抵抗力が弱まり、発生しやすくなります。
症状
頻尿、排尿時の痛み、血尿、下腹部の不快感などがよく起こります。