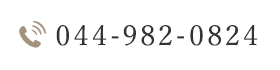更年期障害とは
 更年期は、性成熟期から高年期、老齢期へ移行する時期で、閉経前の5年間と閉経後の5年間を合計して約10年間あります。
更年期は、性成熟期から高年期、老齢期へ移行する時期で、閉経前の5年間と閉経後の5年間を合計して約10年間あります。
女性は加齢に伴い、卵巣の活動が徐々に低下し、最終的に月経が止まりますが、月経が12ヶ月以上来ない状態が続いた時点で、その1年前を閉経と判断します。
日本女性の平均閉経年齢は約50歳ですが、40歳代前半で閉経する方もいれば60歳近くまで月経が続く方もいて、個人で大きく異なります。
女性の体調は、ホルモンが僅かに乱れただけでも、大きく左右されます。
閉経を中心とした10年間の更年期は、主にエストロゲンという女性ホルモンの分泌が大きく変化しながら低下するため、様々な症状が起こり、これらの症状を更年期症状と言います。
そして更年期障害とは、日常生活に影響を及ぼすほど重い症状が出ている状態のことです。
更年期は、女性ホルモンの低下や加齢による症状が起こりやすい時期で、また、介護や子供の独立など、ライフスタイルに大きな変化が生じる年代でもあります。
心身ともに負担が大きくなりやすい時期なため、できるだけ健康的に過ごせるよう、適切に症状をコントロールすることが大切です。
閉経や更年期は、全ての女性にいずれ訪れるものです。
日本女性の平均寿命が90歳に近づいている現在、更年期以降の人生も長くなりつつあります。
更年期障害の重い症状を「もう年だし」と諦めず、適切な治療を受けて上手く更年期を乗り越えることで、その後の生活が大きく変わります。
日々を充実させるためにも、ぜひご一緒に治療を乗り越えていきましょう。
女性ホルモンのエストロゲン
エストロゲンは、卵巣から分泌される女性ホルモンです。
エストロゲンの分泌が大きく変わりながら減少することで、日常に影響を及ぼす更年期症状が起こるのです。
エストロゲンは8〜9歳頃から分泌が開始され、30代半ばになると分泌量のピークを達します。
その後、少しずつ分泌量が低下し、閉経を控えた40代半ばから一気に減っていきます。
エストロゲンの低下は、更年期障害を発症する最大の生物学的要因とされています。
更年期障害の主な症状
更年期障害では、多種多様な症状が見られます。
また、どの症状がどれほど重いのか、どのように現れるかについては、一人ひとり大きく異なります。
さらに、これらの症状は、他の病気によって起こっていることもあるため、正確に見極めることが重要です。
更年期障害の主な症状としては、ほてりなどの血管拡張に関係している症状、それ以外の身体症状、そして精神症状が挙げられます。
血管拡張による症状
ほてり、のぼせ、発汗、ホットフラッシュなど
その他の身体症状
肩こり、頭痛、腰痛、背中の痛み、関節痛、胸が締め付けられる感じ、めまい、動悸、頻脈、冷え、痺れ、疲れやすい、食欲が湧かない、頻尿など
精神症状
倦怠感、意欲の低下、気分の落ち込み、イライラ、情緒不安定(突然怒ったり泣いたりするなど)、睡眠障害(不眠、すぐに起きてしまうなど)
更年期障害の治療
更年期障害の症状には様々な要因が絡んでいますが、生活習慣の見直しと改善により、症状緩和できる患者様も少なくありません。
そのため、初めの問診では丁寧にお悩みをヒアリングしています。
症状が重い場合には、服薬によって症状の改善を目指します。
更年期障害の薬物療法について
 薬物療法にはホルモン補充療法、漢方薬、向精神薬などがあります。
薬物療法にはホルモン補充療法、漢方薬、向精神薬などがあります。
薬の内容は、患者様とのご相談を重ねながら臨機応変に調整します。
ご希望があれば、自費で栄養サプリメントなどの提案も可能です。
ホルモン補充療法(HRT)
 更年期障害は、女性ホルモンであるエストロゲンやプロゲステロンが大きく変動しながら減少することで発症する病態です。
更年期障害は、女性ホルモンであるエストロゲンやプロゲステロンが大きく変動しながら減少することで発症する病態です。
そのため、それらの減少したホルモンをを補うホルモン補充療法(HRT)によって、症状が軽減されることが多いです。
ホルモン補充療法は、特に血管の拡張によって起こるホットフラッシュ、ほてり、のぼせ、発汗などの症状に高い効果が期待でき、それ以外の症状の改善にも有効と言われています。
ホルモン補充療法には、飲み薬、貼り薬、塗り薬などのタイプがあり、連続投与や間隔を空ける投与法など、様々な方法があります。
そのため、それぞれ効果の現れ方も異なるため、その方のライフスタイルに考慮した治療法を見つけることが大切です。
ホルモン補充療法(HRT)のメリットには、加齢によって発症リスクが上がる心臓・血管疾患や骨粗しょう症の予防が含まれます。
特に閉経後の骨粗しょう症は、骨折のリスクにも関係しています。実際に、骨粗しょう症によって寝たきり状態になってしまうケースは非常に多いです。
なお、エストロゲンだけのホルモン補充療法や合成型プロゲステロン(プロゲスチン)併用の治療では、子宮体がんや乳がんなどの副作用が発生するリスクが伴います。
しかし、当院ではプロゲステロンについて、乳がんのリスクをむしろ下げる天然型の保険薬を使用するため、心配はいりません。
医師と相談し、必要性を感じるなら治療を続けていきましょう。
漢方薬の処方
 漢方は、心身のバランスを整えることで複数の症状を少しずつ良くする効果に期待できるものです。
漢方は、心身のバランスを整えることで複数の症状を少しずつ良くする効果に期待できるものです。
また、不定愁訴のように、原因不明な不調を改善する効果にも期待できます。
漢方薬は、複数の生薬を組み合わせた処方があり、体質、体力、症状の起こり方に考慮しながら処方されます。
婦人科では、当帰芍薬散、加味逍遥散、桂枝茯苓丸を主に処方されますが、更年期でもこれら3種類をメインに処方されるケースが多いです。
当帰芍薬散は冷え性でかつ貧血傾向があり、体力が落ちている方に、加味逍遥散は、不安や不眠があって疲れやすく、体力が普通よりやや低い方に用いられます。そして桂枝茯苓丸は、のぼせやホットフラッシュ、下腹部の違和感や痛みが見られ、かつ体力が普通よりある方に向いています。
また、これらの漢方薬だけでなく、温経湯、五積散、温清飲などを処方することもあります。
体質に合えば高い効果が期待できますが、合わない場合には他の処方に変えることも必要です。
向精神薬の処方
 不眠、寝てもすぐに目覚めてしまう、気分の落ち込み、意欲の低下、イライラ、情緒不安定などの症状で日常生活に支障をきたしている場合には、抗うつ薬や催眠鎮静薬をはじめ、抗不安薬などを用いることもあります。
不眠、寝てもすぐに目覚めてしまう、気分の落ち込み、意欲の低下、イライラ、情緒不安定などの症状で日常生活に支障をきたしている場合には、抗うつ薬や催眠鎮静薬をはじめ、抗不安薬などを用いることもあります。
近年では、副作用が比較的少ないとされる選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)やセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)も出ています。
これらは、ほてりなどの症状緩和にも期待できるため、総合的に判断してから処方されることもあります。