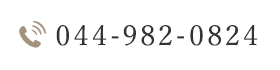片頭痛について
 片頭痛は、何らかの理由によって脳の血管が急激に拡張することで発生し、「ズキンズキン」と脈打つような痛みを伴う頭痛です。
片頭痛は、何らかの理由によって脳の血管が急激に拡張することで発生し、「ズキンズキン」と脈打つような痛みを伴う頭痛です。
最近の研究とCGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)の働き、機序から、片頭痛の発作時にCGRPが関与していることが判明されています。
片頭痛の痛みは、頭の片側または両側に現れ、身動きが取れないほど強い痛みで、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。
吐き気や嘔吐、眠気を伴ったり、光や音、臭いに対して敏感になったりすることもあります。
片頭痛は急に起こり、30分~1時間程度で痛みのピークに達します。片頭痛が起こる際には、視界にキラキラとした何かが見える、頸の周辺がゾワゾワするなどの前兆を感じることがあります。
症状は通常4~72時間程度で落ち着き、治まると普段通りの生活が過ごせますが、発生頻度は患者様によって異なり、数ヶ月に1回程度から週に数回まで様々です。
片頭痛は適切な薬を使うことで簡単に症状を緩和できるため、片頭痛でお悩みの際は、ぜひ当院へご相談ください。
片頭痛の前兆となる症状
片頭痛の前兆が起こることもあります。片頭痛を持つ方の20~30%は前兆を感じると報告されており、中には前兆が見られない場合もあります。
前兆の種類は様々で、光や視野の一部が欠ける(閃輝暗点)といった視覚的なものから、感覚鈍麻、言葉が出づらくなるといった身体的なものまであります。前兆は5分~1時間程度で消失します。
片頭痛が起こる原因
 片頭痛の原因は明確でないことが多いですが、悪天候や精神的なストレス、強いストレスからの解放、過眠、寝不足、ホルモンバランスの乱れなどによって発症します。
片頭痛の原因は明確でないことが多いですが、悪天候や精神的なストレス、強いストレスからの解放、過眠、寝不足、ホルモンバランスの乱れなどによって発症します。
女性の場合、月経周期の影響によって、特定の時期に片頭痛が起こるケースもあります。
片頭痛は血管の収縮と拡張によって発生するため、治療薬には血管に関わるものが多いですが、抗CGRP関連抗体薬のように、神経伝達物質にアプローチして痛みを緩和させる薬もあります。
月経関連片頭痛は難治性のことも多いですが、栄養的アプローチで改善することもあります。お悩みの場合はぜひご相談ください。
慢性片頭痛
慢性片頭痛は、片頭痛に加えて緊張型頭痛など他の頭痛が合併している状態です。頭痛が毎日のように発生し、生活の質が大きく低下します。
慢性片頭痛の診断基準は、月に15回以上頭痛が発生し、そのうち8回以上が片頭痛の特徴を持つ頭痛であると定義されています。
慢性片頭痛の主な原因は、鎮痛剤を長期間使用することで脳の痛みを調整する働きが低下してしまう「薬物乱用頭痛」が関与しているとも言われています。
片頭痛の診断方法
 片頭痛の診断は主に問診を通じて行いますが、場合によってはMRI検査や血液検査を併用することもあります。
片頭痛の診断は主に問診を通じて行いますが、場合によってはMRI検査や血液検査を併用することもあります。
MRI検査は、くも膜下出血や脳腫瘍、もやもや病などを除外するために行い、血液検査は肝機能や腎機能を確認して薬の安全な服用が可能かを調べます。
1回の受診で診断が確定することもありますが、多くの場合、予防薬やトリプタン製剤の反応性や、頭痛ダイアリーのパターンから診断を進めます。
片頭痛と低用量ピル
 前兆がある片頭痛に限っては、低用量ピルの使用は脳梗塞のリスクを高めると言われています。
前兆がある片頭痛に限っては、低用量ピルの使用は脳梗塞のリスクを高めると言われています。
婦人科疾患の治療としてもともと低用量ピルを服用している場合、継続できるかどうかを慎重に検討する必要があるため、かかりつけの婦人科に相談するのが安心でしょう。
代わりとなる治療法がない場合は、そのリスクを説明してご判断を頂きます。
片頭痛の治療
片頭痛の治療には、痛みの前兆を感じたときに内服する薬と、痛みが現れた発作時に服用する薬、そして発作を予防するために内服する薬が用いられます。
薬物療法
前兆を感じた際の治療薬
片頭痛の治療薬として、トリプタン製剤やラスミジタン(レイボー)があります。
これらの薬を痛みの前兆が現れる段階で服用すると、血管の急激な拡張を抑え、その後の頭痛を緩和できます。
ただし、服用するタイミングを掴むのにコツが必要で、上手く服用できるようになるまで少し時間がかかるかもしれません。
トリプタン製剤には様々な種類の薬があるため、医師との相談を重ねながら、ご自身に合ったものを見つけましょう。
また、発作がいつ起こっても対応できるよう、寝室や職場、鞄や財布の中などに薬を常備しておくと良いです。
痛み止め
片頭痛に緊張型頭痛が併発している場合や、トリプタンの服用に失敗した場合、NSAIDsなどの痛み止めを使用することがあります。
しかし、その効果は限られています。
また、市販薬やSG顆粒は薬物乱用頭痛のリスクが高いため、服用する際は服用する錠数に気を付ける必要があります。
予防薬
予防薬を毎日服用すると、片頭痛の発作を防ぐ効果が期待できます。これは片頭痛治療では王道の方法です。
月に3回以上の発作がある場合や、何らかの理由でトリプタンが使えない場合には、予防薬を処方します。
トリプタンの使用頻度が月10回を超えると、薬物乱用頭痛のリスクが高まるため、予防治療が必要です。
片頭痛の予防薬は、本来別の病気の治療薬として作られていた薬が多く、副作用に関するデータが豊富で、そのほとんどは比較的安全に使用できます。
以下に、古典的な従来の内服予防薬についてまとめていきます。
脳血管拡張薬:ミグシス(カルシウム拮抗薬)
脳の血管に選択的拡張作用があり、効果が現れるまで1ヶ月以上かかります。
抗てんかん薬:デパケン、セレニカ
これらは痛み発作に関する脳の興奮をコントロールする薬です。
てんかん治療と同量かやや少なめの量を使用し、服用する場合、定期的な血液検査が必要です。
降圧薬:インデラル(βブロッカー)
高血圧、心不全、不整脈の薬で、妊娠・出産・授乳期にも安全に使用できます。
抗うつ薬:トリプタノール、サインバルタ
トリプタノール(アミトリプチリン)は長年頭痛治療に使用されている抗うつ薬です。
サインバルタは近年発売されたSNRIという抗うつ薬で、どちらも頭痛予防薬として用いられます。
便秘や眠気などの副作用がありますが、眠気の副作用は睡眠の安定を促し頭痛改善に役立つとされています。
新薬:エムガルディ、アジョビ、アイモビーグ
2021年にCGRP関連予防注射薬が次々認可を受けるようになりました。
特に、エムガルディの2本打ちは翌日から効果が出る程の即効性が高く、アジョビは長期効果における評判が良いとされています。
アイモビーグは、上記2剤で腕が腫れる場合に適用される、完全ヒト化抗体の薬です。
1ヶ月に1度の皮下注射が目安ですが、比較的高価です。
漢方薬
漢方薬は片頭痛の改善にも期待できると頭痛ガイドラインに記載されています。
片頭痛の治療では主に、呉茱萸湯(ごしゅゆとう)、桂枝人参湯(けいしにんじんとう)、釣藤散(ちょうとうさん)、五苓散(ごれいさん)、葛根湯(かっこんとう)などが処方されます。これらの漢方薬は、西洋医学の薬と併用することで、より効果が発揮されます。なお副作用を確認するため、定期的に血液検査を受けることが推奨されます。
栄養
片頭痛は、貧血やビタミンミネラルなどの栄養の不足や血糖値の不安定さ、人工甘味料なども原因で起こることがあります。
貧血があれば治療し、サプリメントや点滴でそれ以外の栄養素を補うのも効果的です。
その他
片頭痛は、痛みだけでなく吐き気や嘔吐などの症状がある場合には、その都度対応が必要です。
発作時には制吐剤を用いることがよくあり、制吐剤そのものも頭痛の急性期治療としては有効です。
頭痛について記録する
片頭痛の治療を決定する際には、頭痛の頻度と重症度が重要です。
初診の前には、頭痛についての内容をメモしておくと、診断が迅速に行えます。メモは大体ざっくりとした内容でも構いません。
また、頭痛ダイアリーを使って頭痛を記録し管理すると、片頭痛と緊張型頭痛の区別がつきやすくなり、片頭痛の発作回数も正確に数えられます。
それにより、トリプタンの過剰摂取を予防することも可能です。
また、女性の場合は頭痛の記録をつけることで、片頭痛と月経の関係を理解しやすくなります。
最近では、スマートフォンで頭痛を管理できるアプリも登場しているので、利用するのも良いでしょう。
生活の見直し
規則正しい生活や運動、睡眠の管理、ストレスを溜めないことは非常に重要です。
食事の改善にも取り組む場合は、血管の収縮や拡張に影響を与える食べ物を避けることをおすすめします。
積極的に摂取した方が良い食品
マグネシウム
煎りゴマ、ヒジキ、大豆、玄米、海藻類などに多く含まれています。
ビタミンB2
ウナギ、カレイ、レバー類、ほうれん草、納豆などに多く含まれています。
避けた方が良い食品
チラミン
赤ワイン、熟成チーズ、カカオ製品(チョコレート・ココアなど)、漬物類、発酵食品、燻製魚、鳥レバー、イチジク、ナッツ類、柑橘類には、「チラミン」という成分が含まれているため控えてください。
ナツシロギクの摂取が有効とされる説も唱えられていますが、妊娠中には子宮収縮などを引き起こすリスクがあるので避けてください。
お悩みの場合は早めに受診しましょう
片頭痛は、根本的な原因を解消する治療薬が存在しています。適切な治療を受けることで症状を和らげることが可能です。
また、強い頭痛は他の重篤な病気が隠れている可能性もあるため、強い頭痛でお悩みの場合は、一度は早めに専門医を受診し、適切な治療を受けると良いでしょう。