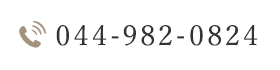日本での骨粗鬆症患者の割合
 日本では他国に比べて高齢化が急速に進んでいます。
日本では他国に比べて高齢化が急速に進んでいます。
平均寿命が延びたことにより、2023年時点で65歳以上の高齢者が全人口の29%を占めています。
また、日本には約1,590万人の骨粗鬆症患者がいるとされていますが、適切な治療を受けているのはそのうちの約8.7%の138万人に過ぎないと指摘されています。
骨粗しょう症は発症しても自覚症状がほとんどありません。
そのため骨折を機に発見されるケースも多いとされています。
骨粗しょう症について
骨粗しょう症は、骨の密度が低下し、骨折のリスクが高まってしまう病気です。骨の強度を考える際には、骨質と骨密度が重要な要素となります。
骨粗鬆症の治療は、骨質と骨密度を改善し、骨折を予防することが非常に重要です。
以下の状態に該当する方は、骨粗鬆症のリスクが高いため、一度当院へご相談ください。
- 何度も骨折したことがある
- ご両親が大腿骨近位部の骨折を経験している
- 飲酒や喫煙の習慣がある(例:毎日ビールをコップ3杯以上飲む)
- ステロイドを常用している、または3ヶ月以上服用したことがある
- 45歳未満で早期閉経した、もしくは関節リウマチ、糖尿病、甲状腺機能亢進症など、骨粗しょう症のリスクを高める病気を発症した方
骨粗しょう症と骨折との関係性
閉経後の女性は、身長の縮小、背中の曲がり、原因不明の腰痛などの症状に悩むことが多いです。
これらの症状は加齢によるものが多いですが、他の原因も考えられます。
骨粗しょう症により、知らず知らずのうちに骨折してしまうこともあります。
特に、25歳の頃より身長が4cm以上縮んだ方は、そうでない場合よりも骨折のリスクが2倍以上にまで上昇すると報告されています。
転倒や骨折により要介護状態に至る方は、全体の80%以上に及ぶともされています。
骨粗しょう症により、50〜60歳の方は手首(橈骨遠位端)を骨折しやすくなります。
さらに年を重ねると、胸椎や腰椎、腕の付け根部分の骨折リスクが高まり、最終的には脚の付け根部分(大腿骨近位部)の骨折リスクが上昇します。
大腿骨を骨折すると、手術を余儀なくされ、骨折が治癒しても後遺障害によって歩行困難になる恐れがあります。
診断
問診や診察の内容、血液検査、骨密度検査などで状態を調べてから確定診断をつけます。
骨密度検査
当院では、足の踵骨を用いた超音波測定法を行います。検査は日本骨粗鬆症学会のガイドラインに基づいて実施されます。
血液検査
骨代謝マーカーを用いた検査は、骨粗しょう症の治療において非常に重要です。
骨代謝マーカーの数値を調べ、骨が正常に新陳代謝しているかをチェックします。
骨代謝マーカーの数値が高い場合、骨密度に問題がなくても骨折のリスクが高まります。
これらの数値を総合的に踏まえ状態を把握し、診断を行います。
また、血液検査の結果から、骨髄腫などの他の原因疾患の有無を確かめることも可能です。
骨粗鬆症の治療
骨粗鬆症の改善において、食事、運動、薬物療法はかなり重要とされています。
食事療法
 塩分や脂肪分の摂取を控え、たんぱく質をしっかりとり、栄養のバランスを考えた食事を心がけましょう。
塩分や脂肪分の摂取を控え、たんぱく質をしっかりとり、栄養のバランスを考えた食事を心がけましょう。
1日700〜800mg以上のカルシウムを食事から摂取するだけでなく、マグネシウム、亜鉛、ビタミンKやビタミンDの摂取も意識しましょう。
最近の研究では、カルシウムだけでなく、マグネシウムや亜鉛、マンガンといった微量元素の重要性も明らかになってきました。
カルシウム等のミネラルが不足すると、骨から溶け出したカルシウムが血管などの組織に蓄積し、糖尿病、動脈硬化、高血圧などのリスクが高まります。
骨粗しょう症の患者様は、既に動脈硬化による心臓病や冠状動脈疾患を合併していることが多いとされています。
そのため、骨粗しょう症だけでなく動脈硬化も悪化を予防するために、骨代謝に必要なカルシウム、マグネシウム、亜鉛、ビタミンD、ビタミンKを適切に摂取することが大切です。
アルコールやカフェインはミネラルの排泄を促してしまうため、なるべく最小限にすることをお勧めします。
運動療法
 運動療法は骨粗鬆症の治療に有効です。
運動療法は骨粗鬆症の治療に有効です。
適度な負荷をかける運動は、骨の強度を高める効果に期待できます。
また、筋力トレーニングにより身体を支える力がつけられ、平衡感覚が身に着けられるため、ふらつきが減り転倒のリスクも軽減します。
週に数回のウォーキングでも効果が期待できるので、無理な運動は必要ありません。
とにかく習慣化することが大切です。
また、脊椎を骨折しないように背筋トレーニングを行うこともおすすめします。
薬物療法
 検査結果や病状に考慮しながら処方を行います。
検査結果や病状に考慮しながら処方を行います。
骨粗しょう症の治療で用いられる薬としては、骨形成促進する注射薬や骨吸収抑制薬としての活性型ビタミンDその他数種類の内服薬、またはその両方の働きを兼ねる注射薬などが挙げられます。
薬の効き方や副作用には個人差があるため、定期検査を受けながら治療を継続しましょう。