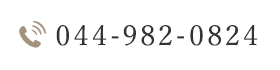肺炎とは
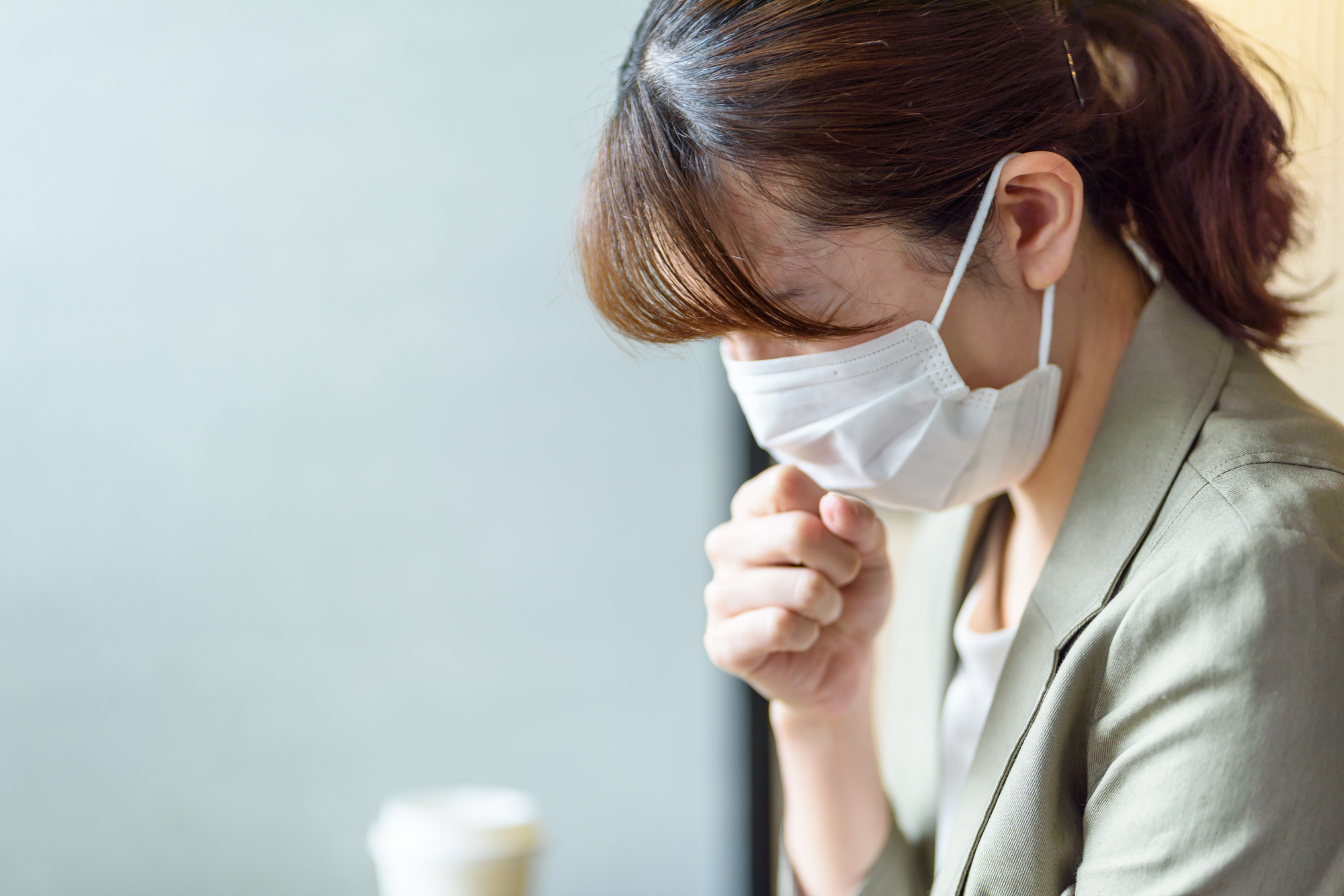 肺炎は、肺に細菌やウイルスが侵入することで、高い発熱や咳、痰などの症状を引き起こす疾患です。
肺炎は、肺に細菌やウイルスが侵入することで、高い発熱や咳、痰などの症状を引き起こす疾患です。
治療せずにいると、肺から全身に菌が広がり、敗血症などの重篤な事態に陥るリスクが高まります。
特に、高齢者や免疫力が低下している方が発症すると、重症化して最悪の場合、命を落とすこともあります。
肺炎は2024年時点で、日本人の死因の第5位を占めている病気です。
初期症状は一般的な風邪と似ているため、適切なタイミングで診断を受け、治療を開始することが大切です。
肺炎が起こる原因
肺炎は、原因となるウィルスや細菌に応じて以下のように分けられます。
| ウィルス性肺炎 | インフルエンザウィルス Covid-19 、サイトメガロウイルスなど |
|---|---|
| 細菌性肺炎 | 肺炎球菌、インフルエンザ桿菌、緑膿菌、クレブシエラ菌、黄色ブドウ球菌など |
| 非定型肺炎 | マイコプラズマ、レジオネラ菌、クラミジア |
熱や咳が続く場合、風邪と肺炎の鑑別が難しいことがあります。
細菌性肺炎の特徴的な症状には、高熱が続く、脈や呼吸が速い、風邪のような鼻水や咽頭痛が強くないことが挙げられます。
一方、非定型肺炎では、咳が続き、比較的痰が少ないことが特徴です。
それぞれ使用する抗生物質が異なるため、正確に見極めるのが重要とされています。
また、脳卒中などで飲み込む力が衰え、食事や唾液を誤嚥することで発症する誤嚥性肺炎や、他の病気の治療による免疫力低下によって発症する日和見感染症もあります。誤嚥性肺炎の場合、口の中にいる大腸菌や嫌気性菌が原因となっているケースが多いです。
肺炎の診断について
 肺炎の診断は、問診や診察で肺炎を疑った場合に、胸部レントゲンやCT、採血検査、喀痰検査を行い、確定診断をつけます。
肺炎の診断は、問診や診察で肺炎を疑った場合に、胸部レントゲンやCT、採血検査、喀痰検査を行い、確定診断をつけます。
採血検査では、白血球数の上昇や炎症反応の高値を確認します。また必要に応じて尿検査(尿中抗原検査)を通して、肺炎球菌やレジオネラ菌の感染を調べます。
さらに、喀痰検査は原因となる菌を同定するために行いますが、結果が出るまでに3〜7日かかるため、症状や画像所見、尿中抗原検査に基づいて原因菌を推定し、治療を開始します。
上記のような感染性の肺炎のほかには、間質性肺炎、好酸球性肺炎、薬剤性肺炎などが挙げられます。
また、まれに肺結核や肺がんを発症しているケースもあります。
これらの病気の可能性がある場合は、レントゲンや採血、CTの結果を総合的に判断し、大学病院などの専門性の高い医療機関にご紹介し、呼吸器内科専門医による診断、加療を受けて頂く必要がある場合があります。
軽症から中等症の方は外来での通院治療で問題ないですが、重症以上の方は入院できる医療機関をご紹介し、そこで治療を開始することになります。
肺炎の治療
 肺炎の場合、抗生物質を用いた治療が基本となります。
肺炎の場合、抗生物質を用いた治療が基本となります。
診断初期には原因菌を推定して、広範囲の菌に効果が見込まれる抗生物質を処方していきます。
細菌性肺炎の場合は、 ペニシリン系抗生物質(オーグメンチンやアモキシシリン)、セフェム系抗生物質(セフトリアキソン点滴)、ニューキノロン系抗生物質(レボフロキサシン)などを処方します。
一方、非定型肺炎の場合は、マクロライド系抗生物質(アジスロマイシンやクラリスロマイシン)、ニューキノロン系抗生物質(レボフロキサシン)を処方します。
薬を使用する期間は5〜7日間です。
細菌性肺炎で用いられる抗生物質
| 種類 | 販売名 | 投与する方法 |
|---|---|---|
| ペニシリン系 | サワシリン、オーグメンチン | 内服 |
| セフェム系 | ロセフィン | 点滴 |
| ニューキノロン系 | クラビット | 内服または点滴 |
非定型肺炎で用いられる抗生物質
| 種類 | 販売名 | 投与する方法 |
|---|---|---|
| マクロライド系 | ジスロマック、クラリス | 内服 |
| ニューキノロン系 | クラビット | 内服または点滴 |
肺炎の治療について注意していただきたいのは「抗生物質の服用をやめない」ことです。
症状が改善しても内服をやめると肺炎が再発したり、抗生物質が効きにくい耐性菌を誘発したりする恐れがあるので、副作用が出ない限り、処方された日数分をしっかり服用しましょう。
また症状を緩和する対症療法として、発熱がある場合は解熱剤を、咳がひどい場合は咳を抑える薬を処方します。
また近年では、抗生物質が効きにくい耐性菌が増えています。
耐性菌が検出された場合、他の抗生物質に変更したり、複数の抗生物質を組み合わせたりします。
肺炎を予防するには
肺炎を予防するためには、以下の点に注意する必要があります。
- 毎日の感染予防:マスクの着用、手洗い、うがいを徹底する。
- 口の中を清潔に保つ:歯磨きや歯周病の予防対策を行う。
- ワクチン接種:肺炎球菌ワクチンとインフルエンザワクチンを接種する。
ワクチン接種をしたから絶対に肺炎にならないわけではありませんが、肺炎の多くを占める肺炎球菌による肺炎とインフルエンザウィルス、肺炎による死亡や入院のリスクを減少させることは証明されています。免疫力が低下しがちな65歳以上の方は、接種を検討することをおすすめします。