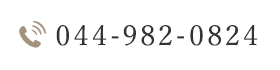- 睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)
- 睡眠時無呼吸症候群と合併する病気
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は2種類ある
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状について
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)を調べる検査
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療方法
- お悩みの際はお気軽にご相談ください
睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)
 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が止まったり(無呼吸)、呼吸が弱くなったり(低呼吸)する状態を繰り返す睡眠障害の1つです。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が止まったり(無呼吸)、呼吸が弱くなったり(低呼吸)する状態を繰り返す睡眠障害の1つです。
- 睡眠中に平均で1時間に5回以上呼吸が止まっている
- 10秒以上呼吸が停止している
これらに当てはまっている場合、SASの可能性が高まります。
無呼吸や低呼吸が繰り返されると、血中の酸素濃度が低下し、脳を含む全身への酸素供給が不足します。
また、無呼吸時に胸腔の圧力が低下し、心臓への負担が大きくなります。
さらに、無呼吸中は脳が覚醒しやすく交感神経が優位になるため、血圧が上昇し、心臓や血管への負担も増加します。
深い睡眠が取れなくなることで、日中の強い眠気や集中力低下を引き起こすこともあります。
日本では、病院を受診していない潜在的なSASの患者様が約200万人いると言われています。
SASの患者様の中には、高血圧や糖尿病などの生活習慣病を併発する方も多く、症状が悪化すると心疾患や脳血管疾患のリスクも高まります。
適切な治療を受けずにそのままにしていると、最悪の場合、命を落としてしまうこともあります。
睡眠時無呼吸症候群と合併する病気
心臓病
調査によると、冠動脈が狭くなって治療を受けた方は、睡眠時無呼吸症候群を発症すると心血管狭窄や閉塞などの発症率が高くなることが分かっています。
また、睡眠時無呼吸症候群の患者様は、そうでない方よりも術後に冠動脈血流の悪化リスクが高い傾向にあります。
脳血管障害
重度の睡眠時無呼吸症候群を持つ方は、脳卒中や脳梗塞の発症リスクが3倍以上になると言われています。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は2種類ある
睡眠時無呼吸症候群は以下の2種類に分けられます。
- 「閉塞性睡眠時無呼吸症候群」(OSAS):気道が閉塞することで発生する
- 「中枢性睡眠時無呼吸症候群」(CSAS):脳幹の呼吸中枢からの指令が一時的に途絶えることで呼吸が止まる
この中で患者数が多いのはOSASです。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状について
特徴的な症状は、睡眠中の無呼吸や激しいいびき(低呼吸)です。
しかし、無呼吸やいびきによって脳が覚醒しても、目が覚めているわけではないため、症状を自覚するケースはほとんどありません。
主な自覚症状としては、次のようなものがあります。
- 起床時の倦怠感
- だるさ、疲労感
- 夜間頻尿
- 喉の痛みや炎症
- 胃腸症状
- 抑うつ症状
- 集中力の低下
- 昼間に生じる、我慢できないほどの強い眠気
睡眠時無呼吸症候群(SAS)を調べる検査
- ご自宅で受けられる「簡易検査」
- 自宅で精密検査が可能になった「終夜睡眠ポリグラフ検査」
上記2種類の検査方法の中から選択します。
簡易検査
診察で睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いと判断された場合、当院から検査装置を貸し出し、ご自宅内で検査を受けていただきます。就寝時に顔と手にセンサーをつけ、睡眠中の呼吸や酸素濃度を測定します。装置を返却後、医師がデータを分析し診断を行います。
睡眠中に1時間あたりの無呼吸と低呼吸の平均回数(AHI: Apnea Hypopnea Index)を計測することで、睡眠時無呼吸症候群の程度が調べられます。
終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)
これは、呼吸運動や酸素濃度の測定に加えて、
- 心電図
- 脳波
- 酸素飽和度度
- いびきの状態
なども詳細に測定し、正確なデータを取得します。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療方法
CPAP(Continuous Positive Airway Pressure)療法
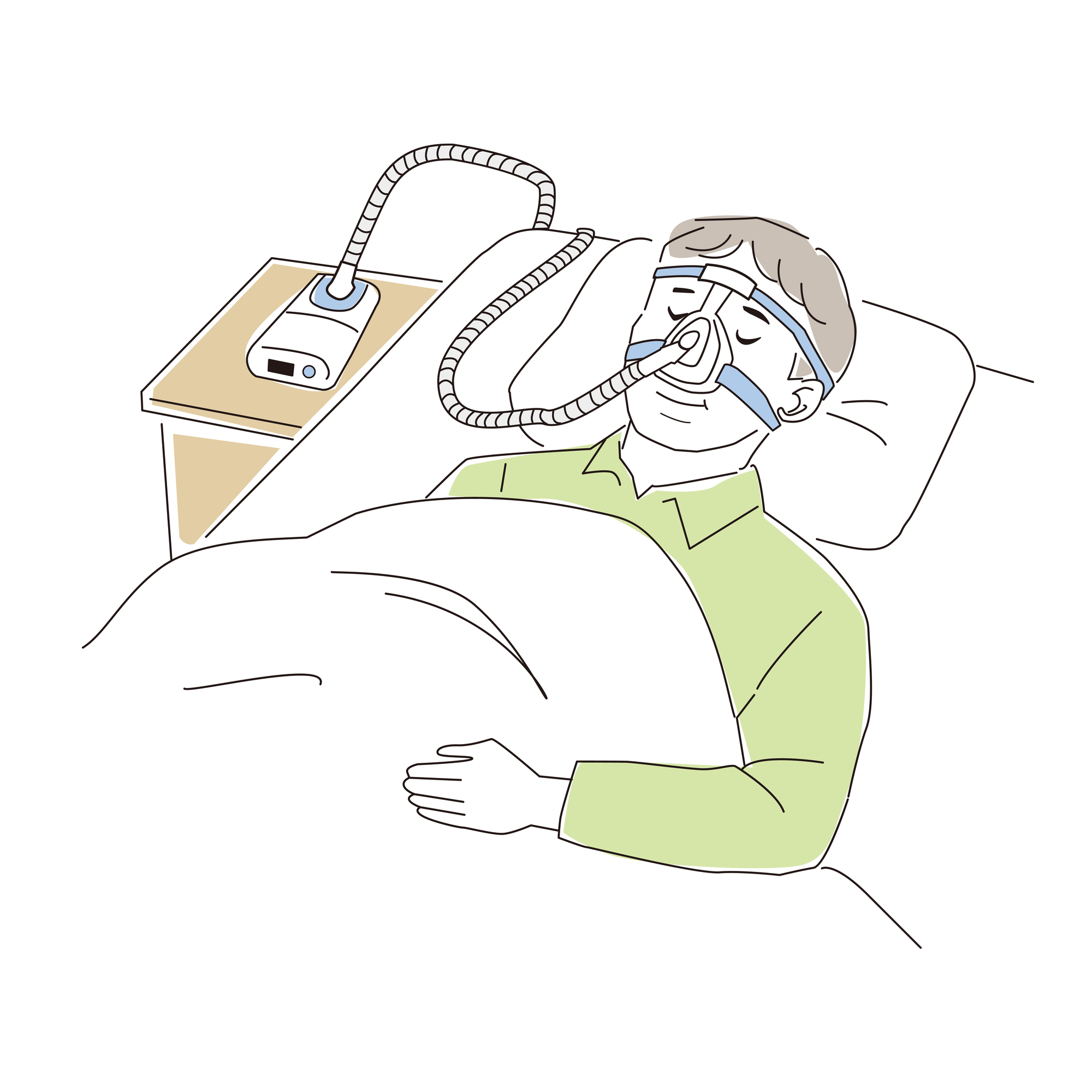 睡眠時に気道の狭窄や閉塞を防ぎ、酸素を体内に行き渡らせる治療法です。
睡眠時に気道の狭窄や閉塞を防ぎ、酸素を体内に行き渡らせる治療法です。
CPAP(持続陽圧呼吸療法)は、睡眠時にマスクを装着し、適度な圧力の空気を送り込むことで気道を確保し、無呼吸やいびきを改善します。
専用装置をご自宅内で使用する方法です。
夜間睡眠中の無呼吸やいびきが改善されると、日中の強い眠気や集中力低下、抑うつなどの症状も軽減されます。
また、心疾患や脳血管疾患、高血圧、糖尿病などの生活習慣病の発症リスク軽減にも期待できます。
診察の流れ
睡眠時無呼吸症候群の保険診療の流れは以下の通りです。
1問診
自覚症状やお悩みについてお聞きします。
2簡易検査
検査機器を借りていただき、ご自宅で簡易検査を行います。
就寝時に顔と手にセンサーを装着し、睡眠中の呼吸や酸素濃度を測定します。
3再受診
検査機器の返却後、1時間あたりに起こる無呼吸といびきの平均回数(AHI: Apnea Hypopnea Index)を計算し、診断を行います。
- AHI数値 20以下:CPAP療法以外の治療法を選択します(マウスピースなど)。
- AHI21~39:より精密検査である睡眠ポリグラフ検査を受けていただきます。その結果を基にCPAP療法が必要かどうかを最終的に判断します。
- AHI40以上:CPAP療法の導入が有効である可能性が高いです。
他の治療方法
生活習慣の見直し
 睡眠時無呼吸症候群は、肥満の方が発症しやすい傾向があります(肥満だけでなく、舌やその他の顎の大きさも影響します)。
睡眠時無呼吸症候群は、肥満の方が発症しやすい傾向があります(肥満だけでなく、舌やその他の顎の大きさも影響します)。
肥満を解消するには、糖質脂質の制限を中心としたカロリー制限や運動によるダイエットが不可欠です。
その際、代謝に必要なビタミンミネラルもあるとより効果的です。
アルコールは筋肉を弛緩させる作用があるため、無呼吸やいびきの原因になるので、寝酒は避けましょう。
また、仰向けで寝ると気道が閉塞しやすくなるため、横向きで寝ると良いでしょう。
外科手術
外科手術は適用されるケースが少ない治療法ですが、SASの原因がアデノイドや扁桃肥大などの時は、摘出手術が有効な場合があります。他にも口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)という軟口蓋(のどちんこ)の一部を切除する手術法もがあります。
しかし、治療効果が不十分であったり、数年後に再発してしまう例もあるようです。
アメリカなどでは、狭い上気道を広げる目的で上顎や下顎を広げる手術も行われていますが、日本でこの手術を行える医療施設は限られています。
マウスピースの装着
 特殊なマウスピースを就寝時に装着し、顎の位置を調整して気道を確保します。
特殊なマウスピースを就寝時に装着し、顎の位置を調整して気道を確保します。
この治療を行うには、歯科を受診しオーダーメイドのマウスピースを作成する必要があります。ご希望の方はご相談ください。
お悩みの際はお気軽にご相談ください
治療が必要な睡眠時無呼吸症候群の方のうち、未受診の方は85%にも上ると報告されています。
睡眠時無呼吸症候群は健康に悪影響を及ぼすだけでなく、睡眠不足による重大な事故のリスクもあり、日常生活やご家族の安全にも深刻な影響を及ぼす病気です。
- ご家族からいびきを指摘された
- 日中の耐え難い眠気や集中力の低下
- 十分な睡眠時間を取っても疲れが取れない
といったお悩みがありましたら、早めに当院をご利用ください。