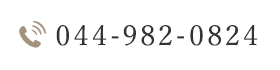女性内科について

女性内科では、女性特有の健康問題を女性医師が診察します。
女性の体は年齢やホルモン周期によって大きく変わり、同じ症状や病気に見えても男性とは異なる原因で起こっているケースもあります。
PMS(月経前症候群)、貧血や冷え性、のぼせ、月経のトラブル、更年期症状、皮膚のトラブル、むくみ、食欲低下、便秘、下痢、不眠症、倦怠感など、様々な症状でお悩みの方はご相談ください。
「どの科で診てもらえばいいのかな?」「検査を受けたけど異常がないと言われた」という方でも大丈夫です。
検査結果や診断名の内容を問わず、生活栄養指導や漢方治療を取り入れた体調改善を実施しています。
また、産婦人科でホルモン補充治療を受けていた方で、「近隣の医療機関で治療を継続したい」という希望がある場合でも、これまでの診療経過に基づいて対応します。
当院ではがんのリスク軽減のために、ホルモン補充を行う場合は合成型でない天然型のホルモン製剤を保険診療で処方しております。
このような症状で
お悩みの方は
女性内科へご相談ください
以下の症状は、月経と関連して起こっている可能性もあります。
- 頭痛、頭が重く感じる
- 冷え、のぼせ
- 喉の違和感(喉に何かが詰まったように感じる)
- 便秘
- 倦怠感、疲れやすくなった
- 微熱、熱っぽさがある
- 貧血
- 動悸や息切れ
- めまい、立ちくらみ、ふらつき
- 皮膚のかさつきや乾燥
- イライラしやすい
- 強い不安感がある
- 憂鬱な気分がスッキリしない
当院で診ている病気・異常
月経前症候群(PMS、PMDD)
月経(生理)が始まる約1週間ほど前から身体や心にいろいろな症状(イライラ、不安、落ち込み、むくみ、頭痛、めまいなど)が起こる状態です。これらの症状は月経の開始とともに弱まったりなくなったりします。
月経のある女性のおよそ70~80%は月経の前に何らかの不快な症状を感じるといわれていますが、PMSやPMDDはその症状の程度が強い状態です。
原因の1つとして、女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンが黄体期に急激に低下する時に脳内のホルモンや神経伝達物質の異常を引き起こすことが上げられています。しかしストレス等それ以外の要因も多くあると言われています。
更年期障害
女性は50歳前後になると月経が不規則になり、その後閉経を迎えます。
この時期から女性ホルモンの減少が始まり、卵巣機能も低下していきます。これに伴う様々な症状が更年期障害です。
更年期を過ぎると症状は徐々に消えていきますが、女性ホルモンの減少により、閉経後は骨粗鬆症や高脂血症のリスクが高まります。これらのリスクを考慮しながら、食事、運動、漢方薬、栄養サプリメント、ホルモン剤などを使って症状の改善を図っていきます。
月経異常
平均的な生理周期は28日程度です。生活習慣やストレス、体調不良などによって周期が変動することもありますが、2~3日早くなったり遅れたりする程度でしたら、特に心配する必要はありません。
しかし、25日より短い場合や38日より長い場合は、体の不調が隠れているサインかもしれません。
ホルモンバランスの乱れは、生活習慣、ストレス、冷え、体重の急激な変動など、色々な要因によっても引き起こされます。
周期が大きく変動している場合には、婦人科の病気が隠れている可能性も疑われますので、原因をしっかり確認し、適切な治療を受けることが大切です。
月経困難症
生理痛は、月経時に起こる下腹部や腰の強い痛みを指し、これが重くなると月経困難症と呼ばれます。
実際には、月経時に全く症状がないという女性はほとんどおらず、多くの女性が下腹部痛、腰痛、頭痛、吐き気、嘔吐、胃痛、乳房の痛み、便秘、下痢、めまい、食欲不振、気分の不調などの症状に悩まされています。
もし症状が重くなった、以前より強く感じたようになった場合は、子宮や卵巣の病気が隠れている可能性も考えられます。
一人で抱え込まずに、ぜひ当院へご相談ください。
注:当院では婦人科的内診やエコー検査は行っていないため、他院婦人科にての検査をご紹介させて頂くことがあります。
過活動性膀胱
過活動膀胱とは、突然トイレに行きたくなり我慢するのが難しい、日中や夜中に何度もトイレに行く、トイレまで我慢できずに漏らしてしまうなど、排尿(おしっこ)に関わる症状が現れる病気です。
女性は出産や加齢によって子宮、膀胱、尿道などを支えている骨盤底筋と呼ばれる筋肉が弱くなった場合などに起こりやすく、40歳以上の女性の約8人に1人が過活動膀胱があることが分かっています。
当院では、生活指導、膀胱訓練、骨盤底筋訓練などをまず行い、効果不十分の場合は薬物治療を開始して経過を見ていきます。
骨粗鬆症
骨粗鬆症とは、骨の代謝バランスが崩れ、骨形成よりも骨破壊が上回る状態が続き、骨がもろくなった状態のことです。
原因としては、骨を形成するカルシウム、マグネシウムなどの必須ミネラルの不足や、カルシウムの吸収に必要なビタミンDなどのビタミンが十分にとれていないことなどが挙げられます。
また適度な運動によって骨に一定以上の負荷をかけないと骨形成におけるカルシウムの利用効率が悪くなるため、運動不足も骨粗鬆症の要因となります。
一般に高齢女性の発症リスクが高くなっていますが、それは閉経後、女性ホルモンである骨吸収を抑制するエストロゲンと、骨芽細胞の活動を刺激し骨形成を促進するプロゲステロンが激減するためです。
診断するうための検査としては、骨折歴の問診や骨密度検査、カルシウムやリンなどのミネラルや骨代謝マーカーを含む血液検査、必要な方は胸椎腰椎Xpなどを行います。
治療としては保険診療では数種類の内服薬、注射薬がそれぞれの方の状態に応じて使えます。
年齢によっては天然型の女性ホルモンの補充療法もお選び頂けます。